ほぼ日の学校長だよりNo.65
「いやしけ吉事(よごと)」
昨日(1月16日)は、私にとって、ふたつ大きな出来事が重なりました。ひとつは前回の「学校長だより」でお伝えしたように、「万葉集講座」の講師として岡野弘彦さんをお迎えしたことです。今年7月で95歳になられる岡野さん。お風邪なぞ召しませぬように、雪など降って静岡県伊東市からお見えいただくのに支障が出ませんように――と祈るような思いでした。
願ってもない快晴、お元気でおいでになりました。

もうひとつは、やはり「万葉集講座」の講師のひとりである永田和宏さんのご推挙で、宮中での「歌会始の儀」(午前10時半~)に陪聴者として参加する機会を得たことです。永田さんは2004年から選者を務めておられます。もちろん私は、初めての体験です。ちなみに岡野さんは1983年から2008年まで選者をなさっておられます。
ふたつのビッグ・イベント。いずれも「速攻」で書くというよりは、ゆっくり感想をまとめたいと思います。そこで今回は、1月11日に行なった岡野先生をお迎えするためのウォーミング・アップ――「予習茶話会」のこぼれ話を書くことにいたします。なにぶん初の試みでしたし、受講生に告知したのが12月の講義の後。きっと都合がつく人だけの、ささやかな集まりになるだろうと思っていました。
ところが、フタを開けてみると、99人クラスのうち、何と60人が集まりました。こちらも気合を入れて臨まないわけにはいきません。
まわりに岡野さんの話をすると、何人かが女優・樹木希林さんのテレビ番組(東海テレビのドキュメンタリー番組)、あるいはそれを劇場用に編集した映画「神宮希林 わたしの神様」を観ていることがわかりました。
2013年、伊勢神宮が20年に一度の「式年遷宮」を迎えた年。樹木希林さんは初めてお伊勢参りをし、伊勢神宮にゆかりの人や場所を訪ねます。その姿を追った作品です。
そのなかで、樹木さんが「会いたい人」として訪ねてゆくのが岡野さんです。きっかけは、次の一首を読んだことでした。
あまりにもしづけき神ぞ血ぬられし手もて贖(つぐな)ふすべををしへよ
岡野さんの第2歌集『滄浪歌(そうろうか)』(1972年)に収められた一首です。1945年1月、“赤紙”で召集を受け、岡野さんは九十九里の海岸防備のため、茨城県で任務につきます。8月、終戦を迎えます。ひと月ほど、部隊での残務処理をした後に、9月半ば、三重県の郷里に帰ります。ひと晩を実家で過ごすと、すぐに翌日、旅に出ます。真っ先に訪れたのが、伊勢神宮でした。実家がお伊勢さまともゆかりのあるお宮の社家ですから、小さい頃からお伊勢さまには格別の親(ちか)しさがありました。
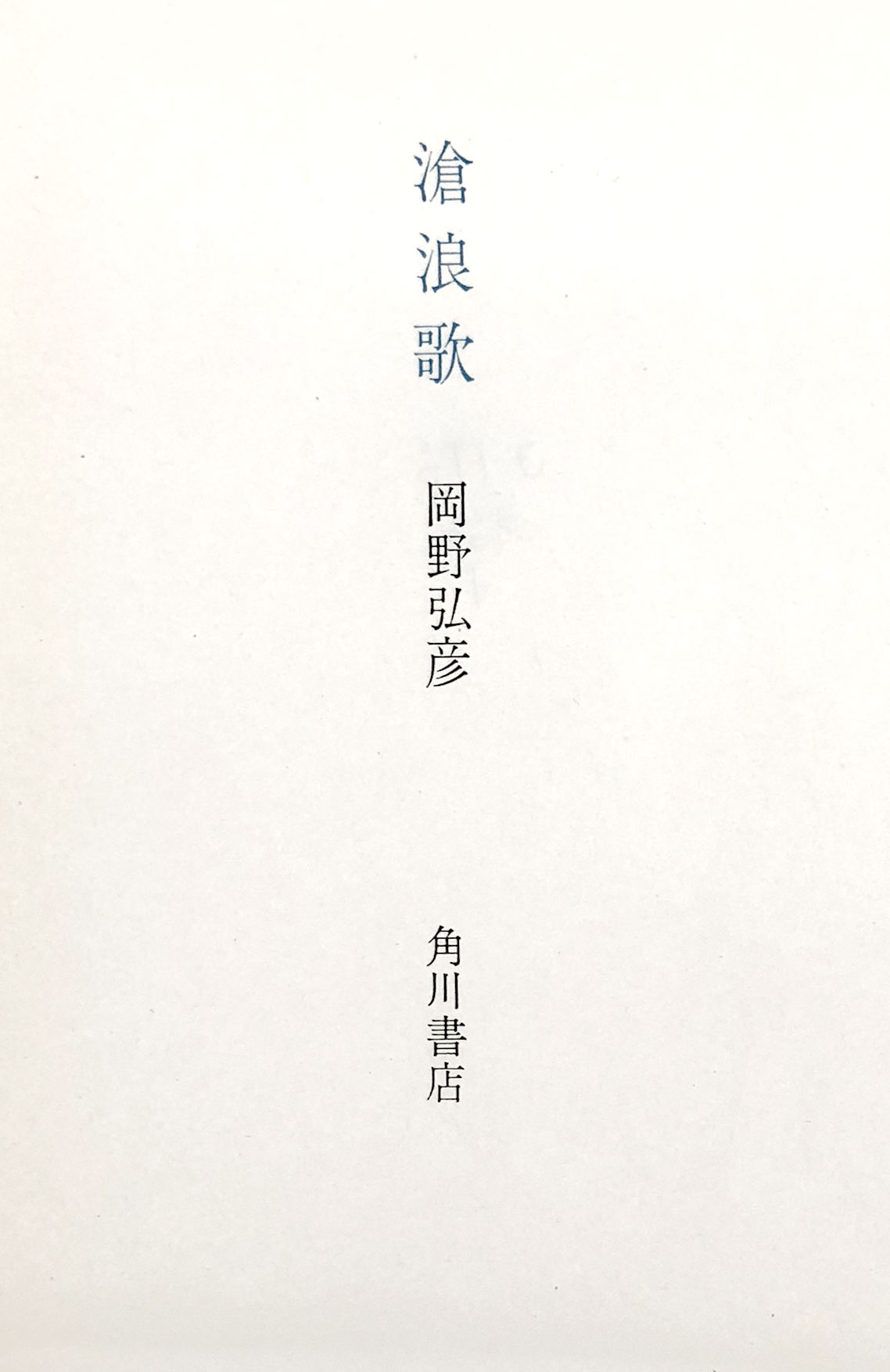
内宮にお参りし、賽銭箱の前の砂の上で、30分ほど跪(ひざまず)いて祈っていたそうです。終戦直後の伊勢神宮には、参拝者はほとんどいませんでした。その時、岡野さんの胸に去来したのはふたつの思いだったといいます。
戦争中、「神風が吹く」ということばをどれほど聞かされたことか。戦況が思わしくなくなればなくなるほど、いっそう「神風が吹く」「神国日本は神風が吹いて守ってくれる」と繰り返されました。なんと都合のいい合言葉だったことか。なんとも虚しい思いに駆られました。
伊勢神宮をつつむ気配は、戦前も、戦時中も、戦争に負けた戦後のいまも、何も変わりがないようでした。清らかで、静かで、何も変わらない。そう思うと、また虚しい気持ちがこみ上げてきました。
あまりにもしづけき神ぞ血ぬられし手もて贖(つぐな)ふすべををしへよ
神さま、あまりにもつれないじゃないですか。こんな時、何か言ってくださいよ、という恨みつらみの思いがあったといいます。「あまりにもしづけき」には、神さまに強く求める岡野さんの切迫した胸のうちがこめられています。次のような話を聞いたことがあります。
「自分は幸いにして、外地に行かなくてすんだ。だから直接、自分の手で銃の引き金を引いたり、軍刀を抜き放って、人を斬ったりはしませんでした。けれども、心の中では同じです。敵を殺すことを考えながら訓練に明け暮れ、その覚悟を定めるように言われていました。だから、戦争に負けて神さまの前に出ると、悔しいような、恥ずかしいような思いが交錯しました。神さまに問いかけて、何か答えてほしかった。神さまは何もおっしゃらなかった。傷ついた若者の心に響くことは何もおっしゃらなかった。‥‥この気持ちは長く尾を引きました。人を殺す訓練ばかりして、人を殺すことばかり考えていた若者ではなかったか――この罪悪感をどうしても簡単に心から追放することはできなかった」
樹木希林さんは、式年遷宮の2年後に、ふたたび岡野さんを訪ねます。戦後70年にあたるその年(2015年)に詠まれた「若き特攻隊長」という歌を読んで、です。
白鳥は血潮にぬれて天くだる。機をおしつつむ弾幕のなか
砕かれし機首 引きおこし ひきおこす。エンジンの音 つひに絶えたり
勝つすべのなき戦ひの果てを信じ、神のごとくに、逝きし二十ぞ
とこしへに 老ゆることなき魂は 水漬(みづ)く屍となりて ただよふ
戎衣(じゅうい)のまま わが帰り来し教室に 君が机は ひつそりと在る
二階級特進し 陸軍大尉に任ず。この文言の いきどほろしき
終戦の前年に、「陸軍特別操縦見習士官(略して『特操』)」に志願することを話し合った一人の学友がいました。敗色が深まる戦況の中で、「自分たちが命を犠牲にして戦うほかに、日本を守る方法はないだろう」という友の言葉に、岡野さんも志願を思い立ちます。郷里の役場に必要書類を申請すると、その連絡を受けた父親が、突然、上京してきます。「死に急ぐな」――夜を徹し、最後は「聞かなければ勘当だ」とまで言い放った父の諫止(かんし)に説き伏せられ、志願を思いとどまります。
学友は「特操」を志願し、やがて沖縄戦に動員され、特攻隊長として戦死を遂げます。
特攻機つらねゆきたるわが友の まぼろし見ゆる。天(あめ)のたづむら
「たづむら」は鶴の群れです。歌集『バグダッド燃ゆ』(2006年)に収められた一首です。21歳で死んでいった同級生の面影が、「まぼろしのように見えてくる。群れをなして空を飛んでゆく鶴の群れよ」という歌です。

岡野さんをふたたび訪ねた樹木さんの番組「戦後70年 樹木希林ドキュメンタリーの旅」は、この歌と証言を中心に、「血ぬられし手もて贖(つぐな)ふすべををしへよ」のさらに深い背景をたどります。戦争が岡野さんにとって、いかに痛切な体験であったかということを――。
 ©東海テレビ放送
©東海テレビ放送
ただ重要なのは、岡野さんのこうした感性の下地が、どこで、どのようにして育(はぐく)まれたか、ということではないかと思い、予習会ではできるだけ幼年期の原風景を追ったつもりです。随想集『花幾年(はないくとせ)』(中公文庫)に見事に描かれた世界です。その中で私がもっとも好きな1篇は、「紫華鬘(けまん)」という冒頭におかれた作品です。
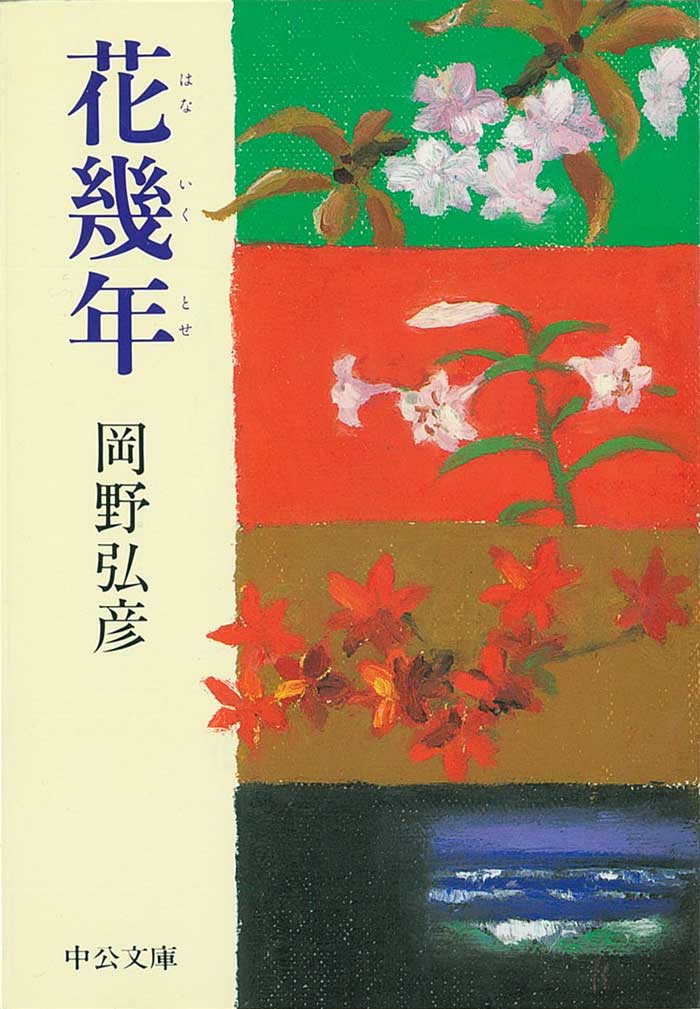
岡野さんのご実家は、伊勢松坂の山奥にある川上山若宮八幡宮という神社の世襲の社家です。隣に、土産物とうどんを売る老夫婦の家があるのみという場所で、小学校のある村までは約3キロ。昼なおうす暗い鬱蒼とした杉林におおわれ、ひっそりと静かな山道は、途中に2つの長くて急な坂があり、谷川にかかった5つの土橋を渡らなければなりません。
電気はなく、ランプの生活。いわば「古代とあまり変りのない」自然に囲まれ、季節のうつろいや、さまざまな山の生きもの、植物に対する柔らかな感性と鋭敏さ、それを受けとめる語彙(ごい)の豊かさを育みながら幼時を過ごします。山に暮らす人びとの喜怒哀楽や、家に出入りする男衆、女衆がなにげなく語る物語を、体感としてとらえながら育ちます。
一方で、早くから字を覚え、夢中で本ばかりを読む少年でした。
<ちょうどその頃、文藝春秋社からたしか八十八冊もある『小学生全集』というのが出はじめた。父はその全集を直接購入してくれた。小包にして送られてくる一冊一冊をむさぼるようにして読んだ。(中略)アンデルセン童話、グリム童話、ギリシャ・ローマ神話、アラビアンナイト、ニーベルンゲン伝説などの世界が、たちまち私の心全体を魅惑しつくしてしまった。それに当時は児童のための文学が盛んで、芥川龍之介をはじめ第一線の作家が、香り高い創作童話を書いて、それが『小学生全集』に収められていた。>

やがて小学校入学の時を迎えます。ここからは、少し長いのですが、岡野さんの文章でたっぷり味わっていただくのがいいと思います。何度読んでもほほえましくなる、岡野さんらしい一節です。
<明日がいよいよ入学式だという夜も、私は興奮で寝つかれないまま、夜遅くまで本を読んでいた。よく磨かれた火屋(ほや)の中で燃える五分芯のランプの炎は、火屋をかがやかせ、上の白い石笠(いしがさ)をかがやかせ、青く半透明な油壺を宝石のように光らせて、部屋全体をやわらかい光に満たしてくれる。その光の下で「アラジンのランプ」の話を読んでいると、たちまち現実は物語の世界の中に吸収せられて、匂いたつような時間が流れはじめる。それは寝てから見る夢の世界よりも、さらに何倍か多様性と魅惑とに満ちた世界であった。
入学式は謹厳な式だけですんだ。その翌日、男子四名女子九名の一年生は、同じ教室で複式授業を受ける二年生と共に、担任の女先生にオルガンを弾いてもらってお遊戯をした。
はじめて同じ年頃の者だけで、しかも男女交互に手をつなぎあって音楽に合わせてするお遊戯というものに、私は次第に夢中になっていった。板壁の粗末な教室はすばらしいお城の大広間となり、王子様・王女様の舞踏会の豪華さの中に居る自分を疑わなかった。そして「これで今日のお遊戯はおしまいです」と女先生が言ったとき、隣に立って面を上気させている可憐な王女さまに対して、りりしい王子さまであるはずの私が、そっと手を伸べ、頬にやさしいキッスをすることは当然の礼儀だと思った。私はジークフリードのような雄々しさと、白雪姫を救いに来た王子さまのような優美さでそれをした。>
午後、家に戻り、裏の竹やぶの中に入ると、萌え出る草木が春の息吹を、新しい生命の力をまざまざと示しています。それを見るうちに、「何とも言いようのない、体の底のむずむずするような感覚とも情緒ともつかぬ思いが、胸を衝きあげるように」湧きあがってくるのを覚えます。
さて、翌日、学校へ行ってみたら何が待ち受けていたか――というのは、おそらく皆さんが想像する通りです。
<‥‥学校へ行ってみると、百二十人ほどの全校生徒の私に対する態度は、異様な熱気をおびていた。そして校内の板壁といわず地面といわずあらゆる空間に、私と相手の女生徒の名とを相合傘の中に入れたいたずら書きが、いっぱい書かれていた。はじめて私は、大きなタブーを犯したことに気がついたが、どうしようもなかった。>
岡野少年は一週間ほど「どうしても学校へ行く気には」なれませんでした。けれども、そこからの反転が、後年の岡野さんを彷彿(ほうふつ)とさせます。
<だが私はそのざわめきの中で、自分の特殊な環境と個性が引き起こしたこの面倒な事態と、徹底的に対決するほかあるまい、みじめな負け犬にだけはなるのはいやだ、と決意していた。一年生にしては健気すぎるほどの覚悟であった。>
こうした感性のルーツを持つ岡野さんが、戦争をはさんで出会ったのが、生涯の師となる国文学者の折口信夫(おりぐちしのぶ)です。1943年10月、出陣する国学院大学学徒壮行会で読み上げられた折口の長歌「学問の道」に触れた衝撃。そして22歳から29歳にかけて、晩年の折口信夫が死去するまでの6年9ヵ月、師の家で起居をともにした内弟子生活――。
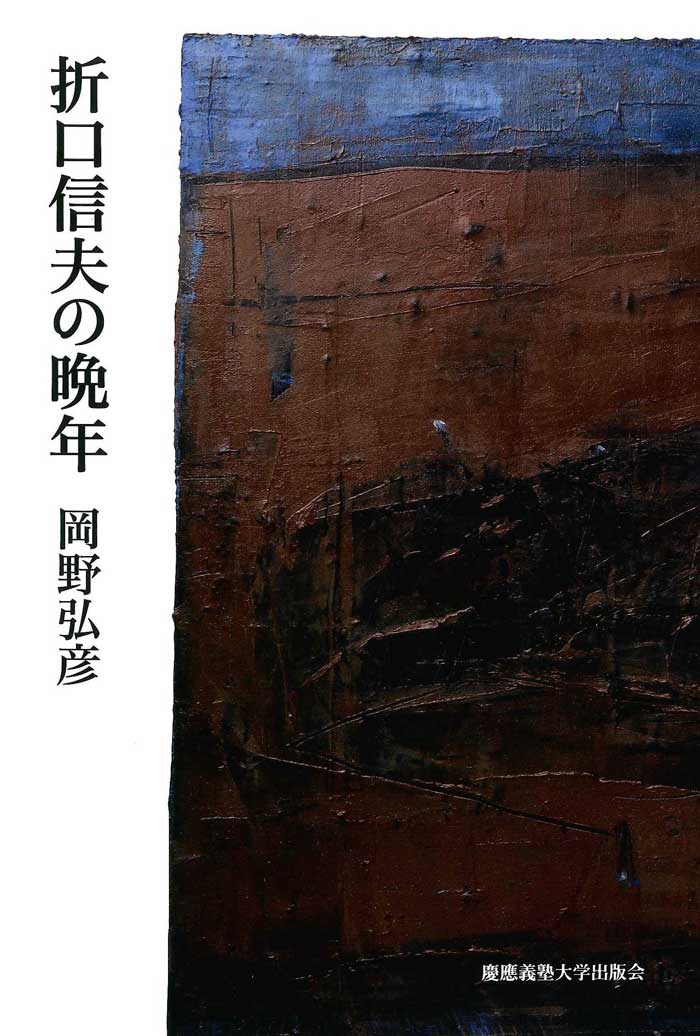
万葉的、あるいは「古代とあまり変りのない」世界に育った岡野さんの感性を、磨き、鍛えたこの師との交流については、また別の機会に触れることがあればと思います。
ともあれ、「新しき 年の初めの 初春の」万葉集講座を岡野さんの「大伴家持(おおとものやかもち)」の講義でスタートできたのは、「ほぼ日の学校」にとって「いやしけ吉事(よごと)」の思いです。
2019年1月17日
ほぼ日の学校長













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。