ほぼ日の学校長だよりNo.69
「字余りの余韻」
休憩をはさまず、ぶっ通しの2時間半! まさかこういう展開になろうとは‥‥。
前回、23歳年長の岡野弘彦さんが、2時間あまり立ちっぱなしで講義なさったことに刺激されたのか‥‥永田和宏さんの授業が、なんだか凄いことになりました。
テーマは山上憶良(やまのうえのおくら)です。万葉歌人のなかでは異色の存在。歌は80首近くが収められていますが、『万葉集』の主流である抒情詩とは明らかに異質です。自然との一体感を歌った作品もほとんどありません。「『万葉集』の歌人たちだけでなく、ひろく日本の古今の詩人のうち、山上憶良ほどに、自然への親しい挨拶を抜きにして詩を作りえた詩人は稀れではなかったか」(大岡信)といわれるほど。

鳥取県倉吉市が平成24年から山上憶良短歌賞を主催しています。テーマは「家族」です。妻や子らへの愛を歌った憶良にちなんで、「家族の絆を見つめ直すとともに、家族愛を育む機会になれば」という趣旨で、短歌の募集をしています。永田さんはこの賞の選者です。
憶良らは今は罷(まか)らむ子泣くらむそれその母も我(わ)を待つらむぞ (巻3、337)
高校生の時に習った思い出があります。「さあ、憶良めはこれでお暇(いとま)いたします。家では子どもが泣いておりましょう。たぶん、その子の母親も私の帰りを待っていることでしょう」。

大宰府在任中、上司である大伴旅人(家持の父)らがいる宴席を、ひと足先に退出しようとして、その理由を詠みこんだ歌です。宴会を中座するきっかけというのは、いまも昔も、厄介です。当時の憶良は70歳を越えていたはず。幼子が待っている、というのはおよそあり得ない逃げ口上だけに、宴席の一同にはウケたことでしょう。どっと笑いが巻き起こったかもしれません。
上野誠さんによれば、万葉集学会が終わった後の懇親会では、長老格の教授が宴たけなわの頃合を見はからい、「憶良らは‥‥」と幹事の若手に声をかけます。すると、幹事は心得たもので、「今は罷らん」の意を汲んで、すぐに帰りのタクシーを準備し、お見送りの手はずを整えます。その時先生はさりげなく、「じゃ、これで」と2次会用の“軍資金”をそっと手渡し、去っていく。これが一種の雅(みやび)なならわしだというのです。
それはともかく、憶良には有名な「子等(こら)を思ふ歌」というのがあります。
銀(しろかね)も金(くがね)も玉(たま)も何(なに)せむにまされる宝(たから)子に及(し)かめやも(巻3、803)
子宝を讃美する歌だといわれます。ところが、この「反歌」の前には序文と長歌があり、これを一組として読むことが重要であると永田さんは指摘します。万葉集研究の伊藤博(はく)氏の見解もそうです(『万葉集釋注三』、集英社文庫)。

<この歌一首だけを取り出すと、子ほどよいものはないという、それだけの歌のように見える。しかしこれは、序文を経、長歌を経てきた、一群の結びであり、序文や長歌と切り離して味わうべき作でないことを知る必要がある。>
背景にあって重要なのは、仏教の思想です。
<‥‥仏教では、一つのもの、とくに我が子などに執着することは煩悩の代表的なもので、道にもとるとされた。仏教に明るかった憶良はそのことをよく知っていて、右の作においても、「子等を思ふ」ことが愛欲の煩悩であることを充分知りながら、しかも、現世の一個の人間としては子への愛着に執(とら)われざるをえない悩みをうたっている。>
<この反歌に述べるところは逆説だと思う。子への我執を煩悩と知る心が深いだけに、憶良は、逆に、子の何物よりも尊いことを絶叫して全体を結んだのだと思う。‥‥そして、それだけに、子どもに対する、憶良の深い愛情が伝わってくる。そういう意味では、一首を、子への無類の愛情を述べた歌と見る一般の解釈にまちがいはない。ただ、あくまで知っておくべきは、汎愛と愛執との相克の重く深い過程を経、愛の苦しみを土台とした上で、一首がなりたっているという一事である。>
憶良が、万葉歌人の中で異彩を放つというのは、こういう“理屈っぽさ”――漢文的知性と倭歌(やまとうた)の叙情性をともに生きた知識人だった――という点にあります。ちなみに、憶良には他の万葉歌人のような、男女間の恋の歌はありません。
逆に、『万葉集』ではただひとつの、貧困を主題にした「貧窮問答の歌」(巻3、892・893)があります。貧者と極貧者との問答を通して、「世の中を生きていくことはいかに辛いものであるか」が、リアルな描写とともに歌われます。
702年に遣唐使として中国に渡り、帰国後は伯耆守(ほうきのかみ)、筑前守(ちくぜんのかみ)などを歴任しながら、管内の政情、民情などを実地に見聞してまわります。この蓄積が作歌に反映されます。抜群の漢詩文の知識を持ち、仏教、儒教の思想にも通じた当代最高の知識人でもありました。
老病貧死の現実を直視し、親の子に対する愛を歌った古代のこのインテリ詩人を、永田さんはどのように評するのか。講義を聞くのが楽しみでした。
さて、先ほどから「釋注」の文章を引用している伊藤博氏(1925~2003)は、永田さんにとって高校時代の恩師です。
花に膨らむ高遠(たかとお)城址に立ちて想う京都府立嵯峨野高等学校非常勤講師伊藤博氏
こういう歌を詠んでいます。出会った当時、先生は大学院を終えたばかりの国語の教師。作文の指導を受け、『若きウェルテルの悩み』の読書感想文を書いたことが印象深いと。後に先生の故郷、長野県伊那市高遠町へ行った時、かつて嵯峨野高校の文芸誌に「高遠物語」という小説を書いた先生を思い出し、詠んだ1首だといいます。45音の字余りの歌ですが、永田さんの連想はここから次の歌につながります。
初々しく立ち居するハル子さんに会ひましたよ佐保の山べの未亡人寄宿舎
佐保は、奈良県の佐保山。戦後間もなく、万葉集研究者で歌人の土屋文明(1890~1990)が詠んだ歌です。こちらも字余りで、41音。4音の差ですが、「土屋文明に勝った!」と永田さんは笑います。
短歌は31音が基本ですが、読む速度を変えることで少々の字余りは許されるのだといいます。字足らずはむずかしいけれども、字余りだと歌がゆったり流れるようになって、うまくいくケースが結構あると。
この日の永田さんの講義が、まさにその字余りを地で行くスタイルでした。憶良の話から、彼の太宰府時代の上司にあたる大伴旅人の話に転じます。旅人と憶良は歌を通じて深い絆を結んでゆくのですが、先に挙げた憶良の「宴を罷(まか)る歌」の次に、『万葉集』に並んでいるのが、旅人の「酒を讃(ほ)むる歌十三首」です。
験(しるし)なきものを思はずは一杯(ひとつき)の濁れる酒を飲むべくあるらし(巻3、338)
なかなかに人とあらずは酒壺(さかつほ)になりにてしかも酒に染みなむ(同343)
あな醜(みにく)賢(さか)しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似む(同344)
この世にし楽しくあらば来(こ)む世には虫に鳥にも我(わ)れはなりなむ(同348)
永田さんが「自分もお酒が好きなので」といいながら、愉快そうに紹介します。そして、酒好きの万葉歌人の代表が旅人だとすると、近代歌人では誰か? 若山牧水ですよね、というので、牧水の酒の歌6首が挙げられます。
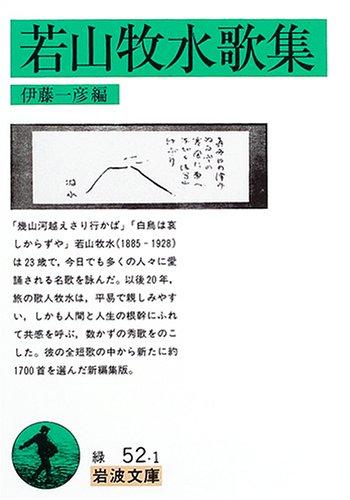
白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ
かんがへて飲みはじめたる一合の二合の酒の夏のゆふぐれ
それほどにうまきかと人のとひたらばなんと答へむこの酒の味
人の世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ
妻が眼を盗みて飲める酒なれば惶(あわ)て飲み噎(む)せ鼻ゆこぼしつ
足音を忍ばせて行けば台所にわが酒の壜は立ちて待ちをる
43歳で亡くなった牧水は、節制すべき酒を、死の直前まで放しませんでした。主治医による「若山牧水先生ノ病況概要」には、最期の数日間の様子が事細かに書かれています。驚くのは、「付記」に記された内容です。9月17日朝に亡くなり、葬儀は19日にとりおこなわれるのですが、死後3日を経過し、当日は「強烈ナル残暑」にもかかわらず、屍臭はなく、顔にひとつの死斑さえなかったとあります。「(斯(かか)ル現象ハ内部ヨリノ『アルコホル』ノ浸潤ニ因ルモノカ。)」。つまり、アルコール漬けだったからではないか、と。
若山牧水賞を受賞した際に、永田さんは、この賞のしきたりとして、牧水の像の上から1升壜で酒を注いだそうです。その牧水は大伴旅人をこよなく愛し、息子に「旅人」と名づけたと。歌がとりもつ遥かな縁(えにし)に、ふと胸が熱くなります。
牧水といえば、なんといっても「白玉」の一首が有名ですが、先ごろ『牧水の恋』(文藝春秋)を著した俵万智さんはこう述べています。
<白玉は、白いものにかかる枕詞。しみじみと、じっくりと、心ゆくまで酒を味わう牧水。こんなふうに静かに楽しんでこその酒だ、という思いがあふれている。そうでない飲み方をしてきたからこそ、の感慨でもあるだろう。体をわざと傷めつけるような乱酔の日々。旅に出る前の東京でのことが、対比的に頭のなかにはあったはずだ。酒とは、こう飲むべきものだなあという結句から、それが感じられる。
ただ単純に、酒好きの酒飲みが秋の夜長にちびちびやっただけでは、名歌は生まれない。この一杯にたどりつくまでの葛藤と苦しみが、目に見えないところで歌を下支えしているのである。>
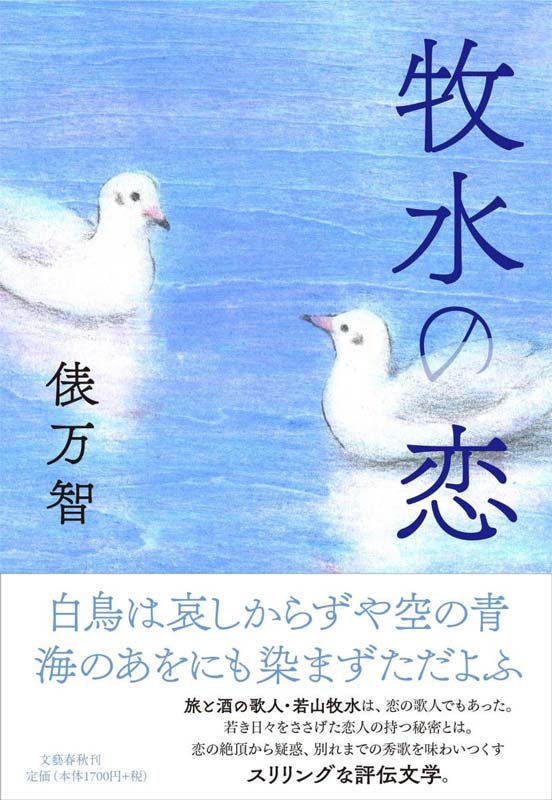
憶良の「子等を思ふ歌」もそうでしたが、「葛藤と苦しみ」を経て吐露される切実な思い――。要を得た解説を聞き、歌の背景を知ることで、読む者の心に「しみとほる」深さが変わってきます。
今回は、俳優の寺田農(みのり)さんにお越し願い、憶良の歌をすべて朗読していただきました。長い漢詩文あり、なじみの薄い仏教用語などがまじった長歌があり、かなり難しい朗読だったと思いますが、深い声で聞く歌の体験は格別でした。

妻を失い、義弟の死を知らされて、「崩心の悲しび」に沈んでいた大伴旅人に対して、憶良が献じた「日本挽歌」(巻3、794~799)の朗読には、とりわけ不思議な感動がともないました。憶良が旅人になりかわって、亡くなった妻への挽歌を精魂こめて歌うというユニークな作品です。前に置かれた長大な漢詩文(無題)と、長歌、反歌5首からなる「日本挽歌」の、「知」と「情」とのコントラスト。
憶良はいったいどんな気持ちでこの歌を作ったのか。歌を贈られた旅人はどういう思いを抱いたのか。皆さん、それぞれに考えていただければ、と永田さんは問いかけます。
そして、2010年に64歳で亡くなった妻、河野(かわの)裕子さんとの相聞歌を、永田さんが紹介します。お互いを歌の対象として、生涯にわたって、それぞれ500首を下らない相聞歌を詠みあったという事実の重さ。披露される折々の歌――。
ことばのもつ力、歌への揺るぎない信頼を語ったくだりは、この日のハイライトでした。いずれオンライン・クラスでご覧ください。もしくは、『歌に私は泣くだらう』(永田和宏、新潮文庫)、『たとへば君』(河野裕子・永田和宏、文春文庫)などをお読みいただければと思います。
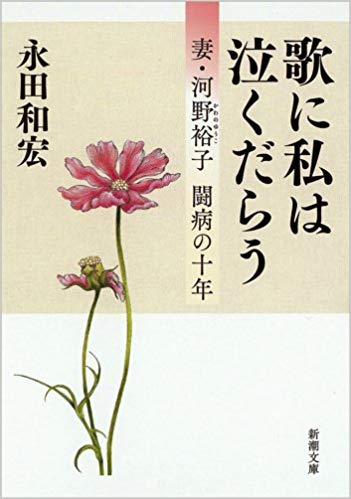
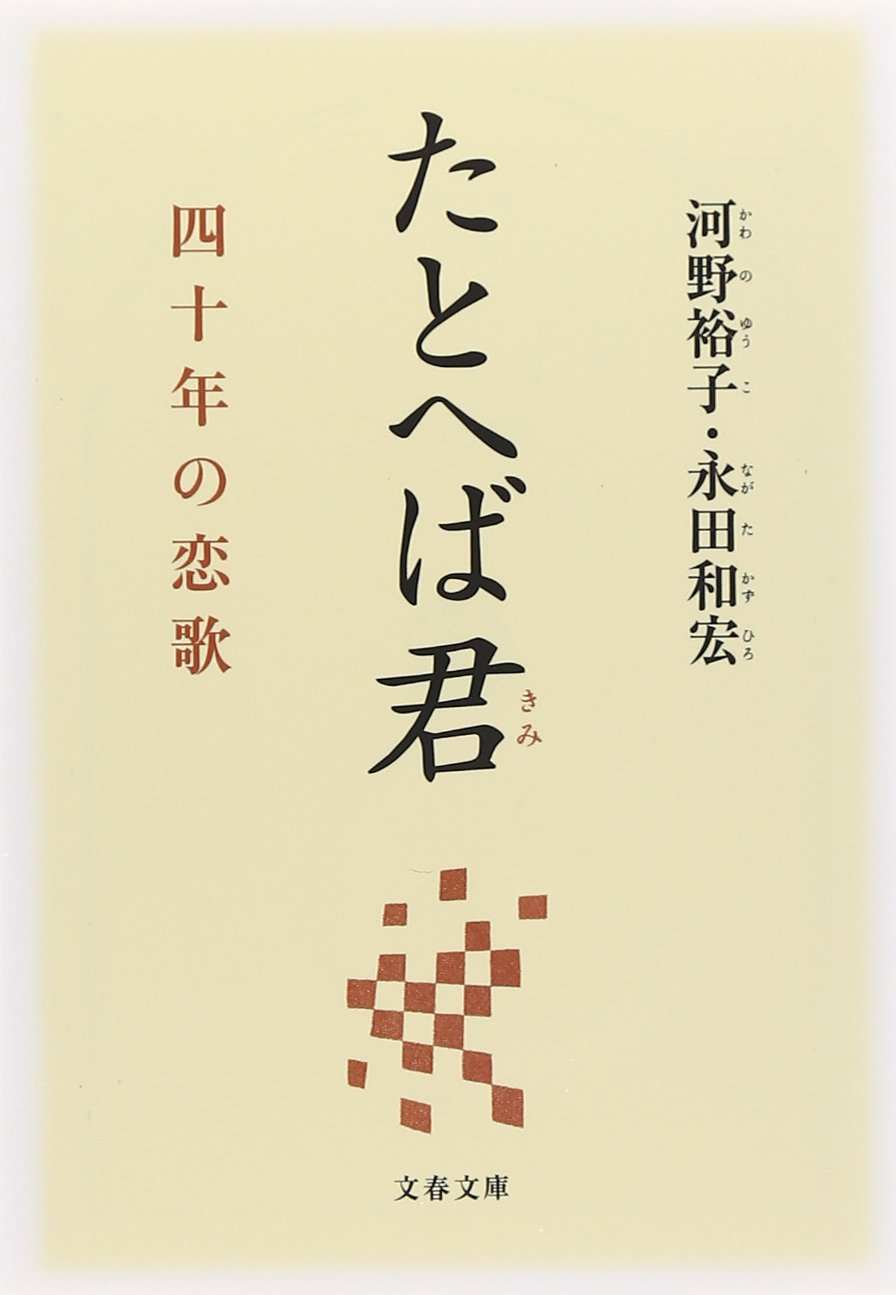
ちょうど私が編集長をしていた雑誌「考える人」で、生物細胞学者としての永田さんの連載を始めようとしていた時でした。河野裕子さんが逝去されました。そこで、科学エッセイの連載を延ばし優先していただいたのが、妻の発病から最期の日までを綴った『歌に私は泣くだらう』でした。

手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が 裕子
死の前日に、永田さんが口述筆記をした河野さんの最後の1首です。今年の8月で、もう9年になるのかと思います。
2019年2月14日
ほぼ日の学校長
*都合により来週はお休みいたします。次回の更新は2月28日の予定です。













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。