ほぼ日の学校長だよりNo.135
ロバート・B・パーカーの「愛」
まだ内緒にしておかなくてはいけない「お楽しみ企画」の準備で、このところ、昔なじんだ懐かしい本を何冊か立て続けに読み返しました。
そんな1冊が、ロバート・B・パーカーの『初秋』(ハヤカワ・ミステリ文庫)です。1981年に原作が発表され、翌年すぐに日本語訳が刊行されます。両親から育児放棄(ネグレクト)された15歳の少年と、私立探偵スペンサーとのまっすぐな心の交流が描かれて、感銘を受けた作品です。
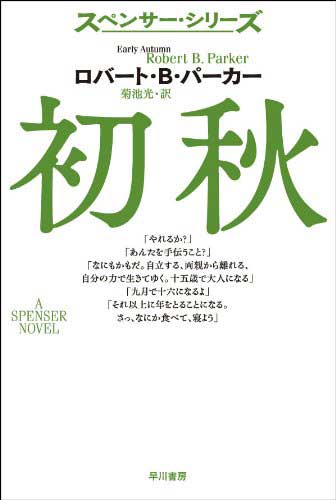
全部で40作あるスペンサー・シリーズの第7作。5番目の『ユダの山羊』(1978年)で初めてこのシリーズと出会った私は、次の『レイチェル・ウォレスを捜せ』(1980年)を発売と同時に即買いし、既刊の4冊も読み終えて、『初秋』の登場を迎えます。

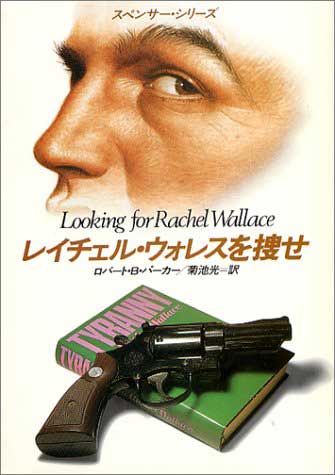
スペンサー・シリーズの代表作だと思います。村上春樹さん、『読まずに死ねるか!』(集英社文庫)の内藤陳さんらプロ筋からも好評で、パーカーの名前が一気に日本で広まります。

とはいえ、うるさ型の多いミステリ界の評価はさまざまでした。「ネオ・ハードボイルド小説の新ヒーローの登場だ!」と絶賛する人がいる一方で、古典的なマッチョの現代版ウェスタン(西部劇)だ、男のハーレクインロマンスだと、揶揄する向きもありました。
ダシール・ハメットのサム・スペードや、レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウに比べると、主役のスペンサーはおしゃべりすぎる、お節介すぎる! 恋人スーザンとの関係もご都合主義だ! 相棒のホークはあまりに腕っぷしが強すぎて、あれじゃクリント・イーストウッドの「ダーティ・ハリー」も顔負けじゃないか‥‥。
誉めているのか、けなしているのか。作品の魅力を語りつつ、ケチをつけて喜ぶような、何ともビミョーな毀誉褒貶がにぎやかに繰り広げられたものでした(それだけ話題になったということです!)。
さて、今回読み直してみて、「えッ!」と思った最初の発見は、作中でスペンサーの読んでいる本でした。
自分の名前はSpencerではなく、Spenser。16世紀の英国の詩人と同じく、cではなくてsなのだ、ということに“こだわり”を見せる主人公です。なかなかの読書家で、会話にシェイクスピアが頻出します。彼が読んでいたのは、バーバラ・タックマン(1912~1989)の『ア・ディスタント・ミラー』(1978年)という歴史書です。
タックマンはアメリカの有名な女性作家、歴史家で、中世から現代まで、幅広い歴史上のテーマを生き生きと描き、多くの読者を獲得しました。1914年6月28日、サラエヴォに響いた一発の銃声から、誰ひとり望まなかった第1次世界大戦がどのようにして勃発にいたったのか――。これを克明に描いてピュリッツァー賞(1963年)に輝いた『八月の砲声』(上下、ちくま学芸文庫)が知られています。
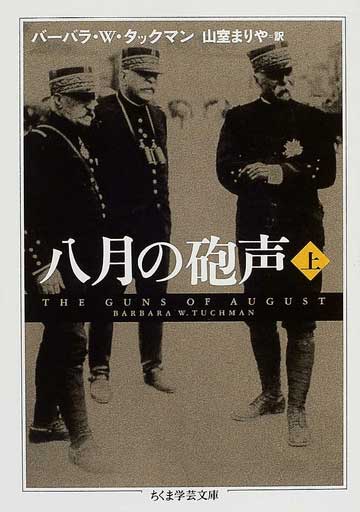
故ジョン・F・ケネディ大統領が1962年のキューバ危機に際し、この本を玩味熟読したという伝説もあり、いまだに政治史の必読書のひとつです。著作のほとんどは日本語に訳され、スペンサーの読んでいた『ア・ディスタント・ミラー』(邦題『遠い鏡――災厄の14世紀ヨーロッパ』、朝日出版社)も、2013年に出ています。
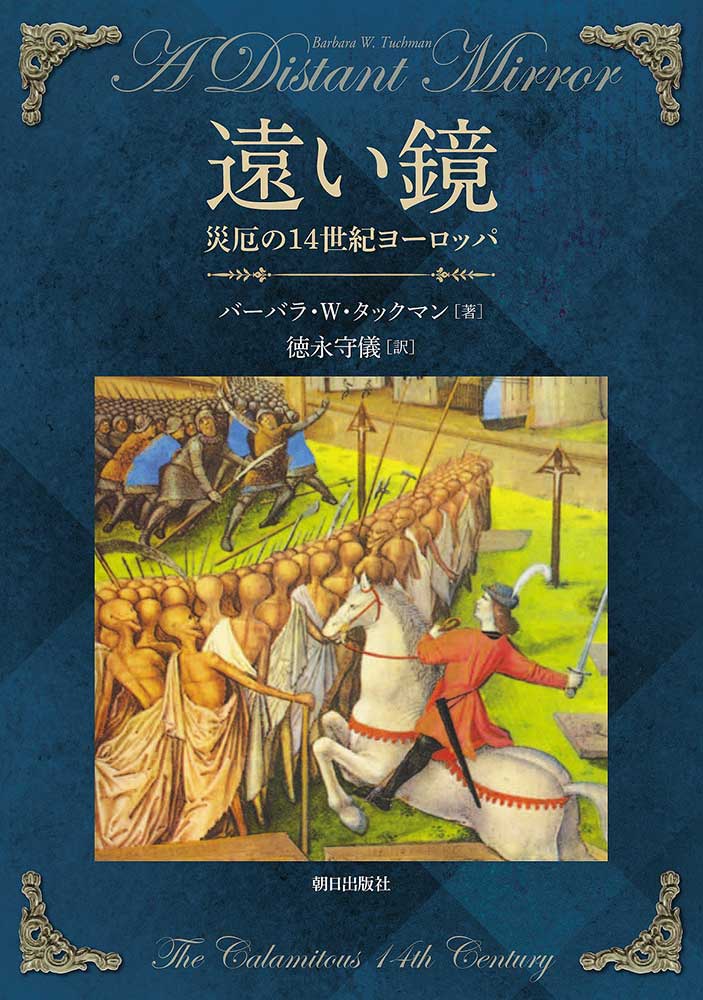
ペストが猖獗(しょうけつ)をきわめ、英国とフランスが100年戦争を戦うなど、まさに「災厄の時代」とされる14世紀ヨーロッパを、人々はどのように生き、未来に備えていたのか。その一大クロニクル(年代記)がこの本です。
「なんで、そんな昔の話を読むの?」と、スペンサーは少年に尋ねられます。
「当時の人々の生活がどんなものだったか、知りたいのだ。読むことによって、六百年の隔たりをこえた継続感が得られる点が好きなんだ」
「おれは、人々の生活について知れば知るほど、人間のことがわかってくる。ある程度の概観がえられる。当時、自分にとってなんらかの価値があると思えるものを手に入れるために、人を殺したり、拷問にかけたり、苦しんだり、努力したり、悩んだ人々が大勢いた。今、彼らが死んで六百年たった。それはいったいどういうことなのか‥‥」
コロナウイルス禍のいまだからこそ、ハッとさせられる著作です。黒死病が蔓延し、1348年~50年だけで、およそ人口の3分の1が死亡したという歴史書を、わが主人公が熱心に繙(ひもと)いてい!
こういう細部の描き方に、このシリーズのさりげない魅力がひそんでいます。スペンサーのつくる料理やビールの飲み方、地元ボストン・セルティックス(プロバスケットボール)や、大リーグ野球の話題にしても――。

ところで『初秋』の物語は、非常に現代的な親子、夫婦、男女の「愛」の問題を、そこでないがしろにされる子どもという存在を介しながら、わかりやすく、ストレートに問いかけている点が魅力です。
離婚した夫が連れ去った息子のポールを取り戻してほしい、という女性からの依頼がスペンサーのもとに舞い込みます。あっさり息子を連れ戻し、彼女のもとへ送り届けると、「あら、こんなに早く帰ってくるとは思ってなかった」と、格別嬉しそうな表情も浮かべません。ボーイフレンドとディナーの約束があるからと、ポールとの晩ごはんをスペンサーに頼むくらいです。
4ヵ月後、再び依頼がきます。ポールが攫(さら)われそうだ、というのです。今度は家に住み込んで、少年の身辺警護にあたります。次第にはっきりしてくるのは、息子を駆け引きの道具に使って、互いに相手を傷つけようとしているだけの父親、母親。
両親からまともに相手にされず、体も痩せて力もなく、自分は何が好きか、何をしたいかもわからないまま、何かといえば、肩をすぼめているだけの無気力な少年。
スペンサーは決断します。すっかり心を閉ざした少年を、この親たちから引き離し、自分が一から鍛え直そう、と。
スペンサーは、恋人のスーザンに語ります。
「わかるかい? おれが言うのは、誰もあの子といっしょに時間を過ごしていない、ということだ。誰も、なにも教えていない、服装や外食といった簡単なことについてすら。無視されている。どのように振る舞うべきか、誰も教えていないんだよ」
「力がまったくないんだ。利口ではない、力強くない、好男子でもない、面白みがないしタフじゃない。あるのはいらいらした感じの底意地の悪さだけだ。それじゃ、なんの足しにもならないよ」
スペンサーがめざすのは、少年の自立です。自分が親代わりを買って出て、彼に誇りと自信を与えようとするのです。
スペンサーは、ポールと一緒にジョギングし、ボクシングを教え、ベンチプレスで鍛えます。森の中に、二人で家を建てることにして、毎日大工仕事に励みます。スーザンにその思いを語ります。
<「あの子供は行動の仕方を一度も教えられていない。なにも知らない。誇りがない。得意なことは何一つない。テレビ以外、関心事はなにもないのだ」
「それで、あなたが教えてやる」
「自分が知っていることを教えてやる。おれは大工仕事を知っている。料理の仕方を知っている。殴り方を知っている。行動の仕方を知っている」(略)
「あなたの話を聞いていると、とても簡単なことのように思えるわ。でも、そうじゃないのよ。相手に習う意志がなかったらなにも教えることはできない」(略)
「どうだい、一役買わないか?」(略)
「相談にのる気はあるわ。でも、あなたにこの問題に深入りしすぎてもらいたくないの。成功の可能性はごく薄いわ」(略)
「彼は短期間に大人になる必要があるんだ。独立できるようにならなければならない。彼にとってはそれが唯一の途なんだ。彼は十五歳で子供であることをやめなければならない。両親はくそみたいな人間だ。彼はこれ以上親に頼ることはできない。自立しなければならないのだ」>

この信念を支えているのは、スペンサー自らの人生体験。彼がどのように育ってきたか、シリーズの読者には明らかです。
スペンサーはワイオミング州ララミーの出身。母親は妊娠9ヵ月の時に、事故に遭い、救急室で死亡します。スペンサーは帝王切開で取り出され、その後は父親と母の兄弟ふたり、つまり3人の男によって育てられます。
父親は大工。ふたりのおじたちは仕事仲間です。スペンサーが生まれた時、父は20歳、おじたちは17歳と18歳。誰もが若い青年でした。
<スペンサーに対する三人の教育の基本は、ちゃんとした“人間”として扱うということだった。彼らはボクシングを教え、本を読んで聞かせ、狩りを経験させと無条件で手放しの愛情を注ぎ、彼に理不尽な圧力がかかったときは徹底的に相手をぶちのめしたものだった。だが、家には女性がおらず、家事はすべて男性がやるもの、男の仕事でもあった。ベッドを直し、掃除をし、洗濯をし、料理もする。そんな風に育って、やがてスペンサーは十歳かそこらのときに、将来のことを考えてくれた父親とおじたちと一緒にボストンへやってきたのだった。>(関口苑生「スペンサーの『物語』」、『ロバート・B・パーカー読本』所収、早川書房)

ポールがこのスペンサー流の教育にどう応じるか? 受け入れるのか、拒否するのか? 期待するような変化を見せるのか?
<「どうしてぼくのことを放っておいてくれないんだ?」
私はまた彼の横に腰を下ろした。「なぜなら、おまえさんが生まれた時からみんなが放ったらかしておいて、そのために今、おまえは最低の状態にあるからだ。おれはおまえをそのような状態から脱出させるつもりでいるんだ」(略)
「なにも、ぼくが悪いんじゃないよ」
「そう、まだ今のところは。しかし、なにもしないで人から見放された状態に落ち込んで行ったら、それはおまえが悪いんだ。おまえはもう一人の人間になりはじめる年齢に達している。それに、自分の人生に対してなんらかの責任をとりはじめるべき年齢になっている。だから、おれは手をかすつもりでいるのだ」
「それとウェイト・リフティングとどんな関係があるの?」
「得意なものがなんであるか、ということより、なにか得意なものがあることの方が重要なんだ。おまえにはなにもない。なににも関心がない。だからおれは、おまえの体を鍛える、丈夫な体にする、十マイル走れるようにするし、自分の体重以上の重量が挙げられるようにする、ボクシングを教え込む。小屋を造ること、料理を作ること、力いっぱい働くこと、苦しみに耐えて力をふりぼる意志と自分の感情をコントロールすることを教える。(略)」
「それでどうなるの?」ポールが言った。「ぼくは、もう少したったら、また帰るんだ。結局なんにもならないじゃないか?」(略)
「たぶん、そういうことになるだろう。だからこそ、おまえは帰るまでに自立できる能力を身につけなければならないのだ」
「えっ?」
「自立心だ。自分自身を頼りにする気持ちだ。(略)おまえのような子供に自主独立を説くのは早すぎる。しかし、おまえにはそれ以外に救いはないのだ。(略)両親が人間的に向上することはありえない。おまえが自分を向上させるしかないのだ」>
本書でのスペンサーは、いつにもまして饒舌です。自説を滔々(とうとう)と述べています。
寡黙な男が多い、いわゆるハードボイルド小説の流れからすると、きわめて異色な個性です。ただ、作者自身は、それにこだわっていない様子です。
むしろボストン大学の大学院で、論文「暴力的なヒーロー、未開原野の伝統と都会の現実、ダシール・ハメット、レイモンド・チャンドラー、ロス・マクドナルドの小説における私立探偵の研究」で博士号を取得した作者であるだけに、ハードボイルドについて、より自由な考え方を持っているような気がします。
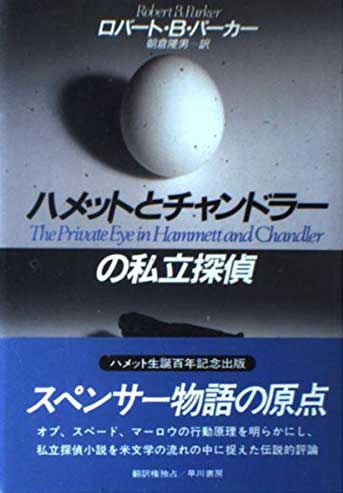
「どちらかというと、冒険小説と呼んでほしい。スペンサーは探偵だが、シャーロック・ホームズとか、エラリイ・クイーンみたいな探偵じゃない。複雑な謎を解かないんだからな。チャンドラーがかつて“隠れた事実を探る一人の男の物語”と言ったことがある。同感だね。男、心情、名誉の行動についての本なんだ。西部小説と同じ伝統だ」(前掲記事中に引用されたインタビュー発言より、『ロバート・B・パーカー読本』所収)
ヘミングウェイ、ハメット、チャンドラーとの違いについても、次のように述べています。
「愛ですね。僕は愛について書いていますし、彼らのうちで誰一人それをやっている人はいないと思います。僕が書くもののほとんどが愛について書かれています。スペンサーとスーザンの関係にしても、両親と子供の関係にしても、夫と妻の関係にしても。(略)愛について書くためにその形式を借りること自体、確かに余りハードボイルド探偵小説の作家がやらないことです。愛を扱ったアメリカのフィクションそのものが、余り多くないのですから」(同上)
久しぶりに出会ったロバート・B・パーカー。歳月を隔てて、より強く響いてくるものがありました。米国北部の初秋の光景、張り詰めた空気。森が闇に溶け込んでいく結びの場面‥‥。
それぞれの読者に、さまざまな思いを喚起させる小説です。改めてロバート・B・パーカーの力量の大きさを感じます。
『初秋』の巻頭には、ふたりの息子(デイヴィッド・パーカー、ダニエル・パーカー)に対する献辞があります。
「二人と共に成長した父より/尊敬と称讃の念をこめて/本書を捧げる」と。
『初秋』の続篇にあたる『晩秋』(第18作)では、「私にとってもっとも大切な/妻と息子たちへ――」ともあります。

『初秋』は、主人公スペンサーが“父性”に目覚めた画期的な転機です。
2020年8月20日
ほぼ日の学校長
*来週は都合により休みます。次回の配信は9月3日の予定です。













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。