ほぼ日の学校長だよりNo.54
「古典的な古典新訳編集者」
前回は村上春樹さんの英語圏進出の話でしたが、今回も翻訳の話題を続けたいと思います。「光文社古典翻訳文庫」の初代編集長・駒井稔さんの『いま、息をしている言葉で。』(而立書房)という本です。先週出たばかりのホヤホヤの1冊です。
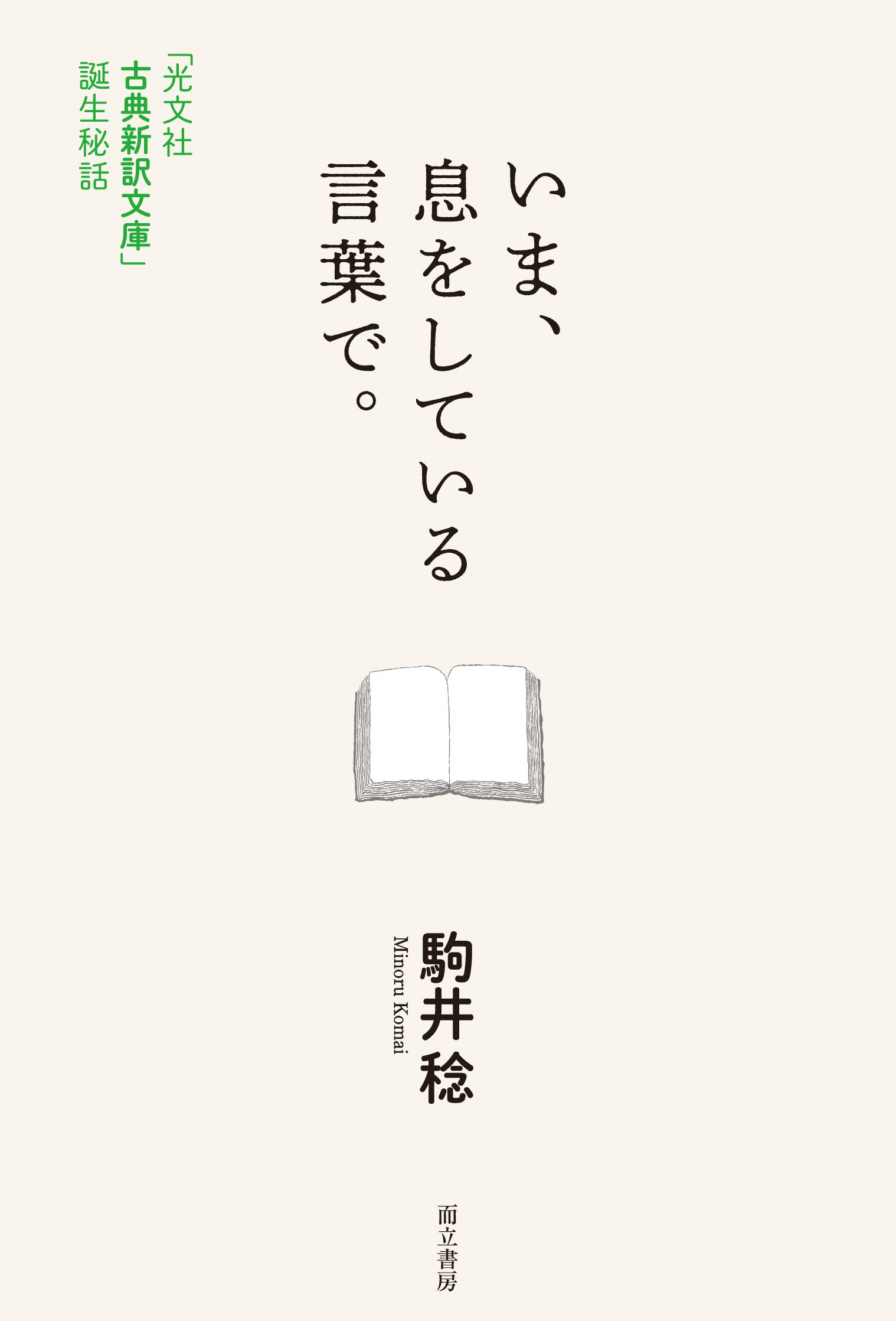
光文社古典新訳文庫は、2006年9月7日に創刊されました。文学のみならず、哲学、社会科学、自然科学など幅広い分野を扱い、日本の古典の現代語訳にも力を注いできました。古典と聞いただけで尻込みしたくなるような、難解、退屈、教養主義的、権威主義的といった負のイメージを解き放ち、「新訳」によって「作品の解像度」を高め、普通に楽しめる本にしてしまおう、というのが狙いです。キモになるのが「新訳」です。
出版界では、ちょうどその3年前に、ひとつの衝撃的な事件が起こりました。
野崎孝訳で定評のあったJ・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』(白水社)を、村上春樹さんが『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(同)とタイトルを大幅に変更し、新たな翻訳に挑んだのです。たちまちベストセラーの仲間入りを果たします。「新訳」という2文字に脚光が浴びせられました。

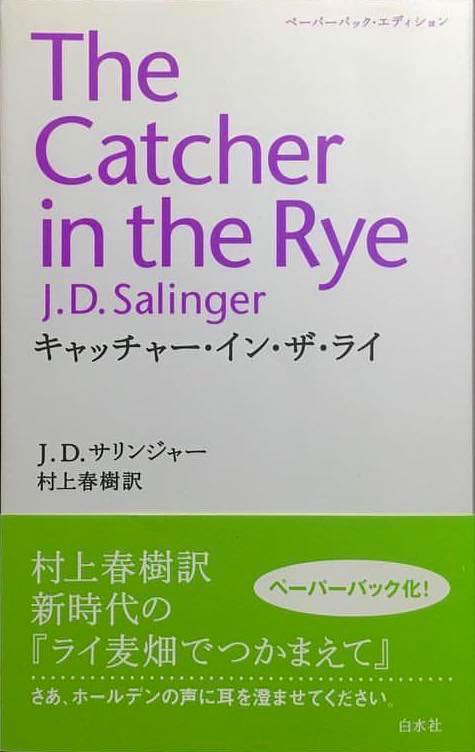
<野崎訳はとても評判の良い翻訳でした。しかしながら新訳が登場したこと、それがあの村上春樹の訳だったことは想像以上のインパクトがありました。(略)それまでは「小説の新訳ってなに?」というのが大方の読者の反応だったのではないでしょうか。(略)「訳文が変わったって? それが何か?」というのが、残念ながらごくごく普通の読者の反応でした。
小説家としての村上春樹は世界で戦える数少ない日本作家でしたし、翻訳小説を読んで育ってきた作家であることはよく知られていました。
その作家が翻訳したのだから、読むべき価値があるのだろう、彼が莫大な時間を小説ではなく、翻訳という仕事に注ぎ込むに足ると考えた素晴らしい作品に違いないと人々が考えたとしても不思議ではありません。>
このように振り返る駒井さんは、同じ2003年の秋口に、古典新訳シリーズの企画書を会社に提出します。年が明けてしばらくすると、社長と話す機会が訪れます。企画書を手にした社長が尋ねます。「現実にはどういう本を出すつもりだ。狙いは分かったから刊行リストを作りなさい」。どうやら手応えは悪くなさそうです。
ほどなく実現した2度目の面会で、100冊のリストを示します。「最終的には世界文学だけではなく、『資本論』や『種の起源』まで出したいと思っています」。真剣な表情でリストを眺めていた社長が、ひとしきり質問を繰り出します。やがて、わずかに沈黙すると、「よし、やってみろ」と、きっぱり断を下します。
それからふと思いついたように、「なんか、シリーズ全体をうまく言い表わすコピーを考えなさい」とも。「例えばどんなものでしょうか」と尋ねる駒井さんに、
「例えばって、うーん、そうだな。つまり読者を惹きつけるようなだな。だから、うーん、例えば『いま、息をしている言葉で。』とか」
「ああ、それいいですね」
「自分でも考えなさい」
こうして古典新訳シリーズのキャッチコピーがたちどころに決まります。本書のタイトルにまで生き続けている「新訳」のキーコンセプトが――。

こう書くと、いかにも順風満帆の滑り出しのようですが、実際に準備が始まってからの道のりは長く、険しかったに違いありません。光文社は『にあんちゃん』(安本末子)、『頭の体操』(多湖輝)、『冠婚葬祭入門』(塩月弥栄子)など、数々のベストセラーを生み出した「カッパ・ブックス」(1954年創刊)の伝統があり、最近では『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(山田真哉)がミリオンセラーになった光文社新書(2001年創刊)など、ポピュラーな出版物では無類の強さを発揮します。しかしながら、古典の出版となると、会社としての蓄積がはたしてどれほどあるのか、正直、外部からはうかがい知れませんでした。
創刊と同時に、いきなり亀山郁夫訳『カラマーゾフの兄弟』が驚異的なベストセラーになるなど、ロケット・スタートを切った古典新訳文庫ですが、シリーズとしての持続力、航続距離の問題は未知数でした。編集長の熱意や見識、志だけではどうにもならない課題がいくつも思い浮かびます。編集スタッフの陣容、チーム力、あるいは組織的なバックアップ体制の問題、外部の翻訳者、デザイナー、装画家などとの協力・信頼関係、そして最後は「時の運」が味方するかどうかも大きな勝負の分かれ目になります。

本書はその間の経緯をできるだけニュートラルに書き留めようと努めています。結果として見えてくるのは、外部で私たちが考えていた以上に、素晴らしいチームワークで難局を乗り切り、地道にシリーズを運営してきたという実態です。
<50歳になった私は、信じられないくらい元気でした。この年齢で新しいことを始めるのは冒険であると周囲には思われていたようですが、本人は一向に気にしていませんでした。>
創刊直前の超多忙の日々を送りながら、編集長は部員を前に力説します。
「徹底的に読者の立場に立って編集し、古典のイメージを変えて見せようではないか」(老舗の古典ブランドに対抗して)
「知ったかぶりをしてはいけない。こちらには誇るべき歴史も十分な教養もない。だからこそ分からないことを分からないと勇気を持って言うべきなのだ」(翻訳者には読者代表として向き合え!)
ときに自分をドン・キホーテのように感じたという駒井さん。どんな調子で喋っていたか、光景が手に取るように浮んできます。私も雑誌編集長として、乾坤一擲の大勝負に臨んだ経験がないわけではありません。このあたりの気分はよくわかります。
ただ、この本を読んで何に一番驚いたかというと、駒井さんのことはよく知っているつもりでしたが、これまで古典新訳文庫の成り立ちについて、彼と本質的な話は何一つしてこなかったということです。たくさんしゃべる機会もあったのですが、それはもっぱら個別の作品についてでした。古典を新訳で届けるにあたって、駒井さんが何に力点を置き、どういう工夫を凝らし、本の体裁、訳者の人選、作品のラインナップ、本づくりの細部にいたるまで、いかに全体をプロデュースしたか、改めて尋ねたことはなかったのです。
ところが、いまはまったく違います。そういう試行のプロセスこそ、まさに尋ねてみたいポイントです。古典をいかにたのしく学ぶか――「ほぼ日の学校」を運営しながら、日々考え続けている問題だからです。
全部はとても紹介しきれないので、駒井編集長の語録から、いくつか刺激的な発言を拾ってみましょう。
・「先を急ぐばかりの20世紀が終わり、いまは混迷の時代。読者は本質的なものへと向かっている」(創刊時のコメント)
・「翻訳が一つしかなくて、しかもそれが自分に合わなければ、その人は作品を読む機会を失ってしまう。でも、新訳によって選択肢が増え、自分のテイストに合った翻訳を選べるようになる」(同上)
・「従来の文学全集や思想書の全集のような体系に則った作品選びは絶対に避けようと思っていました。あの教養主義的な匂いがしたとたん、読みたくなくなるのが古典だという強い確信があったからです」
・「もっと自由に、もっとしなやかに古典と向きあうためには、時間と空間を自在に行き来しながら面白そうなところから、あえて言えばつまみ食いしていくのが正しい読み方だと考えたのです」
・「翻訳調の難解な文章は、実は日本語としての文章表現の未熟さに帰するところが大きい」
・「読める訳文を実現するためにはどうしたらよいのでしょうか。私の答えは明快です。翻訳における無用な難解さを排することに尽きます」
誤解のないように! これらは決して“新訳マッチョ”の暴言ではありません。事実は、まったくその逆です。
<最初にお断りしておきたいのは、私たちは先行訳、つまり既訳に対する敬意を失ったことはないということです。今日とは比べものにならない困難な環境のもとで、限られた辞書や資料を駆使して、その時代における最良の翻訳を目指した先人たちの苦闘には最大級の敬意を払ってきたつもりです。そのうえに積み重ねる形で、最新の研究成果や新しいテクスト、さらにはネットなどを駆使しながら、既訳を乗り越える新訳を作っていくことが古典新訳文庫の責務であると考えたのです>
なんだ、ここにも書いてあるのか、と思う記述もありました。「ほぼ日の学校」が11月から始める「万葉集講座」の「開講のことば」を、私は次のように書き出しました。
<世界史に刻まれた人間ドラマを
漫画で読んでいた同世代の女子に対し、
われら男子は出遅れました。
何といっても、池田理代子さんの『ベルサイユのばら』です。
スタートの躓きはその後も尾を引いて、
最近ではヤマザキマリさんの
『テルマエ・ロマエ』にまで及んでいます。
日本文学へのアプローチも同様です。
大和和紀さんの『あさきゆめみし』で
『源氏物語』に親しむでもなく、
恥をしのんでいうならば、
里中満智子さんに『万葉集』の時代を描いた大作
『天上の虹』があることを、ついこの間まで知りませんでした。
不明を恥じるほかありません。
ところが、読みだすと実におもしろい!
いまさらながら、夢中になって一気に読みました。
万葉人が、俄然、隣りの人のように近づいてきました!>

漫画の効用を説く、似たような記述が本書にもありました。また、古典新訳の嚆矢(こうし)となった橋本治さんの『桃尻語訳 枕草子』に対する賛辞にも同感です。リアルのイベントを重視する点もまったく同じです。駒井さんには「たらればさん、SNSと枕草子を語る。」(ほぼ日の学校番外編、10月29日)をご覧いただきたいくらいです。

「本書を読むことが古典と出会うためのささやかなきっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。とりわけ若い世代に古典を手にとってほしい」(まえがき)
この思いに支えられ、古典新訳文庫の創刊の意図、その後の経緯を丁寧に綴ったのが本書です。10年にわたって編集長をつとめた感慨を、おごらず高ぶらず、謙抑(ドストエフスキー訳の先人、米川正夫氏のキーワード)に語っているのが、読後感の爽快さにつながります。
それともうひとつ。新米の頃、著者は酒場で先輩に尋ねられたそうです。「お前はどんな編集者になりたいんだ」と。唐突な質問に、なぜかマジメに、そして簡潔に答えたといいます。「ぼくは古典的な編集者になりたいんです」と。
この場合の「古典的」は、古典新訳文庫の古典ではないはずです。編集者のオーソドックス、正統、つまり多少「無頼」であろうとも、王道を歩む編集者になりたい、といった意味でしょう。意味するところは、私たちの世代にとっては郷愁のような記憶につながります。願わくは、若い世代にもその魅力やかぐわしさを多少なりとも感じてほしい、というのが著者のひそかな願いのように読めました。
2018年10月25日
ほぼ日の学校長












