ほぼ日の学校長だよりNo.119
吉村昭の眼
画面に流れる映像を見て、言葉を失います。東日本大震災の発生から、一夜明けた2011年3月12日。朝のテレビニュースは、前日各地を襲った津波の様子を伝えていました。
海から押し寄せるおびただしい水の塊が、防波堤を越え、車や家屋を押し流していきます。水は、さらに川をさかのぼり、集落を呑み込み、次々と家屋を圧し潰します。
水の寄せ方も容赦ないものですが、やがて沖に向かって急激に引き始めた水の勢いに、さらに自然の恐ろしさを見せつけられます。
陽の光にさらされた被災地の変わり果てた姿にも、言葉を奪われ、うちのめされます。
茫然としながら思い出したのが、吉村昭さんの『三陸海岸大津波』(文春文庫)でした。1970年に初めて中公新書で刊行された時は、『海の壁――三陸沿岸大津波』というタイトルです。
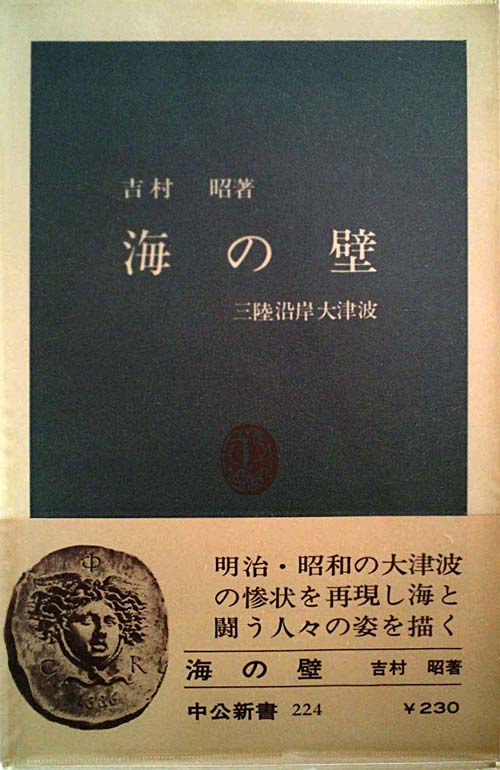
東北をともに旅した時、「海の壁」の由来を吉村さん自身から聞いていました。
津波の押し寄せ方は、海岸の地形や湾口の開いている方向などでさまざまだが、「屏風を立てたようにやってくるもの、山のように盛り上がってくるもの、重なり合うようしてやってくるもの」――いずれにせよ、リアス式海岸の湾口から流れ込んだ海水は、奥に進むにつれて急激にふくれ上がり、容赦なく襲いかかってくるのだ、と。

<‥‥黒々とそそり立った津波の第一波は、水しぶきを吹き散らしながら海上を疾風のようなすさまじい速度で迫っていた。
湾口の岩に激突した津波は、一層たけり狂ったように海岸へ突進してきた。逃げる途中でふりむいた或る男は、海上に黒々とした連なる峰のようなものが、飛沫をあげて迫るのを見たという。
津波は、岸に近づくにつれて高々とせり上り、村落におそいかかった。岸にもやわれていた船の群がせり上ると、走るように部落に突っこんでゆく。家の屋根が夜空に舞い上り、家は将棋倒しに倒壊してゆく。>
1933(昭和8)年3月3日、岩手県の田老(たろう)村を襲った津波の描写です。
それに前後して、1896(明治29)年6月15日、1960(昭和35)年5月21日の三度にわたり、三陸沿岸は津波被害に襲われます。そのありさまを、数々の証言や子どもたちの作文をもとに再現したのが『三陸海岸大津波』です。
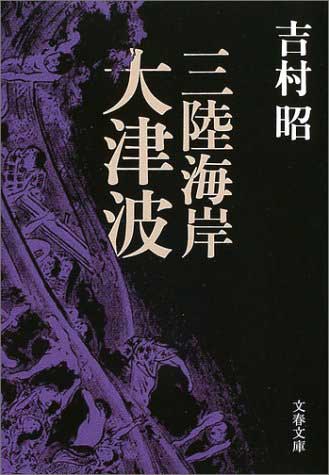
吉村さんの本領は、感情を抑えた硬質でストイックな文体にあります。事実をして語らしめる本書の結びも、この作家ならではの文章です。
<津波は、自然現象である。ということは、今後も果てしなく反復されることを意味している。
海底地震の頻発する場所を沖にひかえ、しかも南米大陸の地震津波の余波を受ける位置にある三陸海岸は、リアス式海岸という津波を受けるのに最も適した地形をしていて、本質的に津波の最大災害地としての条件を十分すぎるほど備えているといっていい。津波は、今後も三陸海岸を襲い、その都度災害をあたえるにちがいない。>
医師の診断のように冷静な分析です。そして、こう結びます。
<私は、津波の歴史を知ったことによって一層三陸海岸に対する愛着を深めている。屹立した断崖、連なる岩、点在する人家の集落、それらは、度重なる津波の激浪に堪えて毅然とした姿で海と対している。そしてさらに、私はその海岸で津波と戦いながら生きてきた人々を見るのだ。
私は、今年も三陸沿岸を歩いてみたいと思っている。>
新型コロナウイルスの感染拡大が話題になりはじめた頃、吉村さんの別の小説が、しきりに頭をよぎりました。完璧な傑作だと思い続けている作品です。
ただ、いまは目に見えない未知のウイルスに、誰しもが言いしれぬ不安と恐怖を感じている時です。この小説を話題にするのは、少し躊躇(ためら)われるところがありました。
『破船』(新潮文庫)。文庫本で230ページほどの、そんなに長くない小説です。北の海に面した貧しい漁村を舞台にした江戸時代の物語――。

村の土地は痩せており、「肥料をあたえても砂礫(されき)の多い土は肥えることもなく」、稗(ひえ)、粟(あわ)、黍(きび)など雑穀程度しか育ちません。蛸、鰯、烏賊(いか)、さんま、そして海草、貝類など、海の恵みでかろうじて命をつなぐ、わずか17戸の集落です。
<村は、海に鋭くせり出した岬の断崖で南を閉ざされ、わずかに北への峠越しの路で他の村落へ通じている。それは、岩場づたいの険阻な路で、深い谷を二つも渉(わた)り、蔓(つる)のからみ合う樹林の中の急斜面をのぼってようやく峠にたどりつく。そうした地勢が、村を孤立したものにさせていた。村の者たちは、その路をたどって漁獲物を他の村落に運び、農作物その他に換えて持ち帰る。が、それらは、家族の者の空腹をいやすには不足であった。
飢えから家族を守るのに容易な方法は、家族が身を売ることであった。峠を越えた隣接の村には、口入れ屋を兼ねた塩買いの商人がいて、まとまった金を身売りの代価としてあたえてくれる。その金で家族の者は穀物を買い入れ、家に運ぶ。
主として売られるのは娘だが、戸主である男も身売りする。>
主人公の伊作は9歳です。父が3年間の年季奉公で回船問屋に売られ、母、弟、妹、生まれたばかりの女児の5人で暮らしています。赤ん坊が産まれた時に、父は年季奉公に出る決意をしたのです。
そんな村にも数年に一度、途方もない恵みがもたらされます。白米の俵、絹織物などの衣類、清酒、砂糖などの嗜好品、家具、什器(じゅうき)、ロウソクなどを、「お船様」が与えてくれるのです。
海が荒れた冬の夜、村人は浜で夜通し、製塩のための火を焚き続けます。伊作も「村おさ」に指名され、晴れてその一員に加わります。しかし、「塩焼き」は表向きの理由です。
積荷を満載した船は、沖で荒海に難儀します。その時、「塩焼き」の火を目にした船びとは、それによって人家のある浜だと知り、舳先を岸に向けて進めます。しかし、入江に大きな船が近づくと、浜の前面に広がる複雑な岩礁で、船底はたちまち砕かれ、座礁します。
つまり、北西の風が吹きつける夜を選んで「塩焼き」をするのは、船をおびき寄せ、破船をうながすための巧妙な「罠」というのが実態です。
船が岩礁で砕かれると、村人は総がかりでこれを襲い、船乗りたちを始末します。積荷を奪い取り、良質の船材は家の補修や家具づくりに利用します。これもすべて、貧しさゆえの村のサバイバル戦略です。ご法度の収奪と知りながら、村人たちはこの恵みの訪れに“希望”を見出しながら生きています。
秋が深まると、村人総出で「お船さま招き」の儀式をやります。孕(はら)み女が村おさの前に据えられた箱膳(はこぜん)を荒々しく蹴とばし、「お船さま」の到来を祈願するという祭事です。
父が年季奉公に出て2年目の冬。待ち焦がれたお船さまが、7年ぶりに到来します。323俵の米を満載した船でした。命乞いする水主(かこ)たちを口封じのために殺害し、村おさの差配でお宝は各戸に分配されます。
伊作の家は8俵でした。数年間の家計を支える米になります。
<「八俵」
母は呻(うめ)くように言い、かれの顔を見つめた。その眼に涙が湧き、頬を流れた。嗚咽(おえつ)をこらえているらしく、顔がゆがんでいる。
年季で売られた者が村に帰ってきた折には、村おさが貯蔵米の中から応分の米をあたえる。明後年の春にもどってくるはずの父の分も入れると、量はさらに増す。>
そして、次の冬がやってきます。
<その年のお船様を招く孕み女に選ばれたのは、十六歳の小柄な女であった。女は海に注連縄(しめなわ)を投げ、村おさの家で箱膳を足でくつがえした。が、その力は、前年のくらとは対照的に弱々しく、椀に盛られた食物が床にこぼれただけであった。
紅葉が去り、落葉がしきりになったが、塩焼きははじめられなかった。例年になく凪(なぎ)の日がつづき、お船様を招く時化(しけ)は訪れず、塩を焼く意味はなかったのである。
伊作は舟を毎日のように海に出したが、眼にしたことのない一尺近くの魚がしばしばかかった。それは十年に一度か二度初冬にみられるギンと言われる魚で、名称通り鱗(うろこ)が銀色に光り、小骨が多い。老いた漁師たちは、凪の日がつづくこととギンが多くとれることをいぶかしんでいた。>
ここから始まるラストの60ページが、私の頭に「悪夢」のように焼き付きます。村に襲いかかる戦慄すべき災厄を、吉村昭の文体があたかも「記録文学」のように描き出します。それが読む側の想像力を刺激し、ゾッとする光景として残ります。
年明けの1月下旬、2年連続の「お船様」が到来します。村は当然、沸きかえります。しかし、そのお船様は奇妙でした。破船ではなく、流れ着いた老朽船です。船の中に積荷らしいものはなく、中には20人ほどの男女が、全員赤い着物に赤い足袋を身に着け、死に絶えていました。
村人は、一抹の不安を覚えますが、骸(むくろ)が着けていた上等な着物を剥ぎ取って、それを「お船さまの恵み」として配ります。そこから容赦ない災厄が村を襲い、伊作を失意のどん底に叩き落します。

これ以上は内容にあえて立ち入りません。作家は後にこの作品について、短い解説を書いています。
<江戸初期の多くの古記録に、一、二行の気になる記述があり、それを強く意識しはじめたのは、かなり以前のことである。荒天の暗夜の海で難儀する船を、海岸に住む者たちが巧みに磯に誘って破船させ、積荷などを奪うことがひそかにおこなわれていた、と記されていたのである。
そのような記述が、主として日本海岸沿岸の各地に残された記録にしばしばみられ、私はこれを素材に小説を書くことを思い立った。
また、恐るべき疫病であった疱瘡(天然痘)にかかった者からの感染を防ぐため、それらの者を船に乗せて海に流したという記録も眼にして、その両者をむすびつけることで、小説の構想は成った。(略)
歴史文学の範疇に入るのだろうが、古記録に散見する短い記述によって書きあげた虚構小説である。>(『吉村昭自選作品集』第7巻「後記」、新潮社)

疫病に対する無知がいかなる悲劇を生むか。連日、新型コロナの話を聞きながら、この作品を改めて読みました。そして、未知のウイルスという予測不能の不確実性を前にして、「高を括る」のでもなく、玉石混交の情報に振り回されるのでもなく、「正しく恐れる」ことの困難と大切さを思います。
『破船』を読み返しながら、それにいまさらながら気づかされました。

3年の年季奉公が明け、父が山路を帰ってきます。漁に出ていた伊作は、舟の上で視認します。体が硬直し、やがて咽頭(のど)に嗚咽(おえつ)がつきあげます。何も知らないで帰ってくる「父の驚きと悲しみが、胸を刺し」ます。
<かれは、父の悲嘆を眼にしたくなかった。このまま沖に舟を向け、潮にのって遠い所へでも行ってしまいたかった。
体から力がぬけ、頭の中が空白になった。為体(えたい)の知れぬ叫び声が、口からふき出た。
かれは、櫓(ろ)をとると舟を浜の方向に進めていった。>
最後の1行は吉村昭らしい締め括りです。『三陸海岸大津波』が、「私は、今年も三陸沿岸を歩いてみたい‥‥」で閉じられるように、運命に向き合う作家の強い意志を感じます。
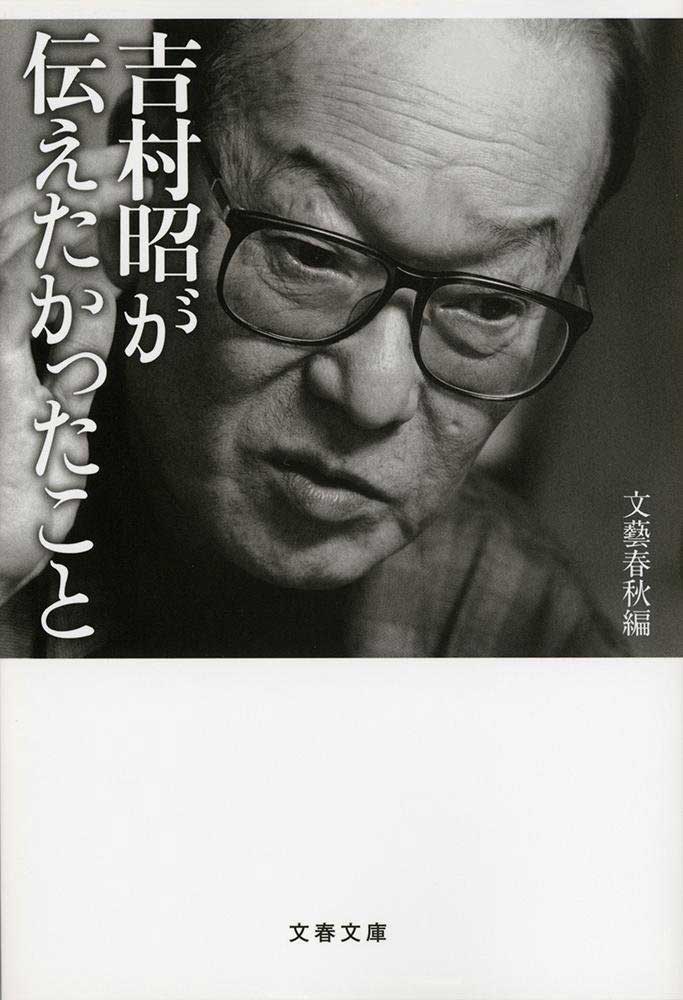
2020年4月2日
ほぼ日の学校長
*当初、3月末までを予定していました「ほぼ日の学校オンライン・クラス」の無料公開を「4月いっぱい!」に延長しました。引き続き、じっくり、ゆっくり、お楽しみいただければと思います。














メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。