ほぼ日の学校長だよりNo.122
忘れられたパンデミック
474ページの大著を、一気にむさぼるように読みました。まさかこんな日が来ようとは!
ながらく積読(つんどく)状態にしてあった速水融(あきら)さんの『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ――人類とウイルスの第一次世界戦争』(藤原書店)を、慌てて探し出して読んだのです。
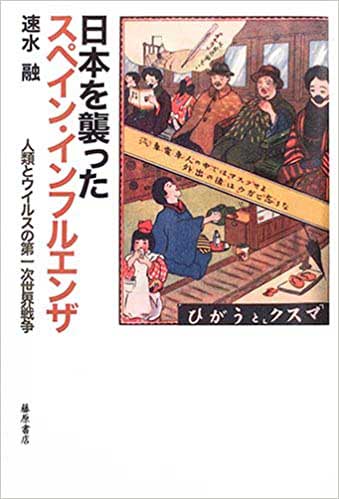
実は、この本の刊行された2006年に、著者である速水さんと直接お話しする機会がありました。その前年に鳥インフルエンザが猛威をふるい、感染症の脅威が取り沙汰された直後です。
速水さんは、感染症の恐怖を語りました。人類とウイルスとの戦いは、両者が存在する限り永遠に続く。新型ウイルスは、「天災」のようにやってくる、忘れた頃に必ずまた‥‥。地震にせよ、新型ウイルスの発生にせよ、人間に自然災害を未然に防ぐ術はない。われわれにできるのは「減災」であって、いかに被害を最小限で食い止めるかだ。それには歴史を知らなければならない。「スペイン・インフルエンザ」に取り組もうと思った所以(ゆえん)である、と。
そんな話を聞きながらも、私はどこかボンヤリしていました。科学や医学の日進月歩を信じるあまり、あるいは無意識にタカをくくっていたのかもしれません。新型ウイルスの持つ意味が、腹の底に響いていなかったと思うのです。
速水さんの著作としても、この本はやや異色の部類でした。日本の近世史研究に初めて「歴史人口学」を導入し、フランスの歴史人類学者エマニュエル・トッドから“日本の歴史人口学の父”と呼ばれた速水さんです。
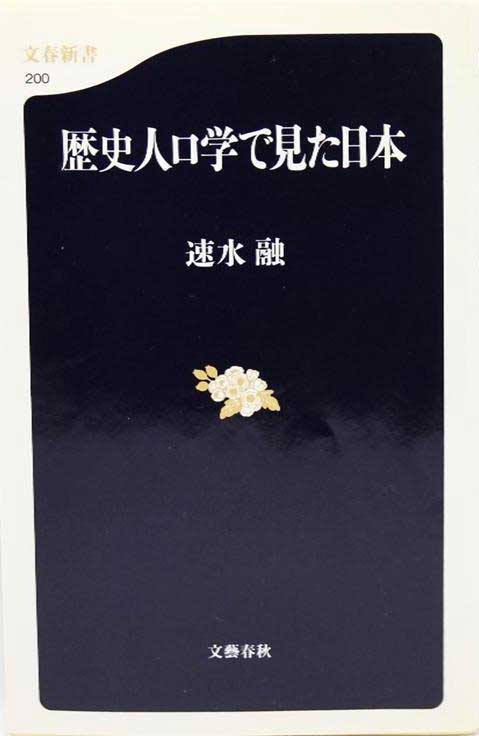
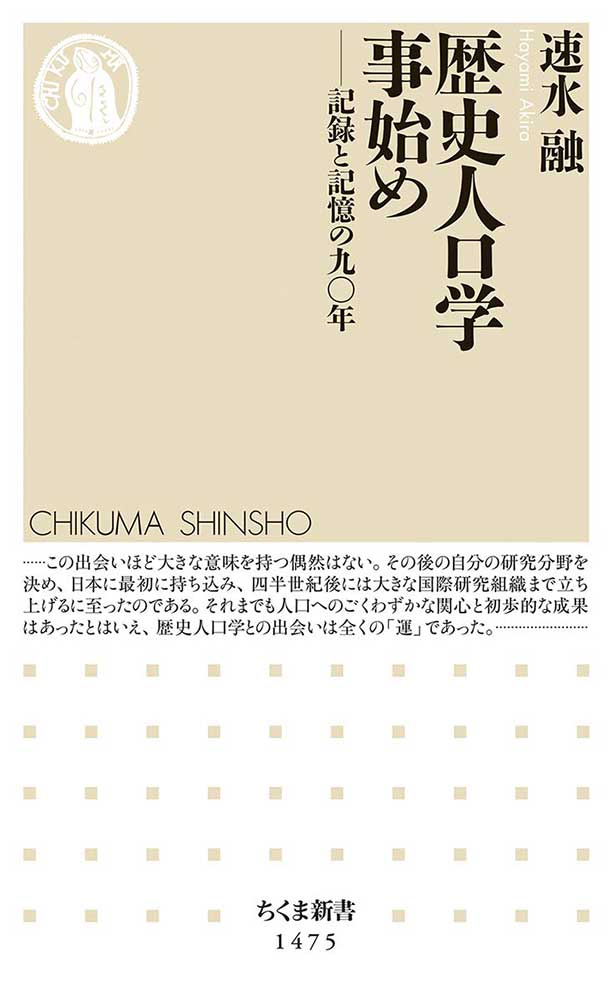
江戸時代の人口動態から新たな経済史研究を開拓してきた従来の著作からすると、大正時代に流行った「スペイン風邪」の研究は意外の感があり、また膨大な文献資料、統計・図表に、正直、恐れをなしたところもありました。こうして、そのまま“積読”になったのです。
それが、まさかこんなに身近な教訓として、切実に迫ってくる日が来ようとは、夢にも思いませんでした。不明を恥じるばかりです。
武者小路実篤に『愛と死』(新潮文庫)という恋愛小説があります。新進作家の村岡は、友人の妹である夏子と知り合います。逆立ちと宙返りが得意だという活発な夏子に村岡は惹かれ、やがて二人は村岡のパリ遊学からの帰国後に結婚する約束をかわします。ところが、日本への帰途、村岡は香港で夏子の急死を知らされます。スペイン風邪が原因でした。

100年前、世界をスペイン・インフルエンザが襲いました。死者は、世界全体で4000万人以上だと言われます。当時の世界の人口が20億人弱ですから、約2%にあたります。
同時期の第一次世界大戦の戦死者が約1000万人だったことを考えると、いかに被害が甚大だったかがわかります。スペイン・インフルエンザは、なんと、その4倍の命を短い期間に奪ったのです。「これは20世紀最悪の人的被害であり、記録のある限り人類の歴史始まって以来最大でもある」と速水さんは指摘します。
スペイン・インフルエンザは日本でも猖獗(しょうけつ)を極めました。内務省衛生局『流行性感冒――「スペイン風邪」大流行の記録』(東洋文庫、平凡社)によると、死者は38万5000人とされ、この数字が定説化しています。ところが、著者はこれを過小とみなし、その統計の不備を補います。別の方法で試算すると、少なくとも45.3万人が死亡したと推計されます。ただし、これは「内地」に限った数字です。

当時、戦争や併合によって日本領土になっていた樺太、朝鮮、台湾、さらに租借地であった関東州の、いわゆる「外地」の死者はというと、少なく見積もっても28.7万人にのぼります。内地・外地を合わせると、実に74万人に達します。
それにもかかわらず、「歴史教科書に全くとり上げられず、いくつも刊行される日本の歴史、近代日本の歴史といったシリーズものにも登場しない。(略)詳しい年表にようやく一行を見出すのみ」というのです。
さらに驚くべきことに、「このスペイン・インフルエンザについて、日本ではそれをタイトルとした一冊の著作もなく、論文すらごく少数あるに過ぎない」と。
<‥‥なぜ日本ではかくもスペイン・インフルエンザは“忘れられて”しまったのだろうか。その被害たるや、やや誇張すれば、有史以来最大で、しかも統計資料・記述資料ともにかなり豊富に残されているのだから誰も採り上げないのは不思議でさえある。>
そこで、「歴史を追う者の仕事」として取り組んだ研究が本書です。一読、その徹底ぶりに驚嘆します。公的な統計や記録だけでなく、当時の新聞記事を根こそぎ集めようと力を注ぎ、全国紙と地方紙を「一府県最低一紙の方針」で収集し、ほぼ70%の府県の新聞記事を集めています。また、軍隊、地域、企業、学校、文壇などの資料も可能な限り集めています。
よほどの使命感、学問的な情熱、強い意志の賜物(たまもの)だと思われます。愛弟子の礒田道史さん(国際日本文化研究センター准教授)が述べています。
<二〇〇〇年に七一歳で「文化功労者」になった後も、そして二〇〇九年に「文化勲章」を受章した後も、先生の研究意欲は衰えませんでした。晩年始めたのは、感染症の歴史分析です。鳥インフルなどが脅威となるなかで、人口の数%も殺した感染症の歴史を研究することは、戦争による死者を減らすのと同じくらい重要だと思われていたのでしょう。>(「わが師・速水融が変えた『江戸』の貌」、「文藝春秋」2020年2月号)
甚大な被害にもかかわらず、スペイン・インフルエンザはなぜ忘れられたか、という理由のひとつは「スペイン風邪」という名称のせいだと思えます。風邪とインフルエンザでは医学上全く異なるものであるにもかかわらず、当時は「流行性感冒」と報じられます。風邪というと、どうしても軽く受け流されてしまいます。
さらに「スペイン」という地名! 本書によって初めて知るのですが、この病気の発生はそもそもスペインとは何の関係もありません。現在でも、原発生地は不明なのです。
<スペインにとって不運だったのは、他のヨーロッパ主要国が交戦中で、どの政府も自国でインフルエンザが流行していることを発表しなかったのに、中立国なるが故に、流行の状態が世界に知れ渡ったことである。(略)そのため、このインフルエンザは、この頃から世界的に「スペイン・インフルエンザ」と呼ばれる破目になった。そのことの裏には、ヨーロッパでは、何でも悪いことはスペインのせいにするという悪癖も手伝っていた。>
私たちにとって「忘れてならない」教訓のひとつは、スペイン・インフルエンザは3回やって来た、という事実です。1回目は1918(大正7)年5月から7月で、高熱で寝込んだ人はいたようですが、死者を出すにはいたりませんでした。大相撲夏場所で全休者が5人もいて「角力風邪」の名前がつきますが、この時の流行は、症状の軽い「春の先触れ」と呼ばれます。
次が、同年10月から翌年5月頃までの「前流行」と呼ばれる本格的な襲来で、26万人の死者を出します。速水さんはこう述べます。
<日本は島国であり、国外からのインフルエンザ・ウイルスの侵入をオーストラリアのように、一時的にせよ防止できたかもしれない。しかし、その措置は全くとられなかった。それどころか、新聞には何故か猛威を振るっているアメリカやヨーロッパのインフルエンザ流行に関する記事は全く掲載されなかった。インフルエンザが猛威を振るっていることを、政府自身、十分知っていたかどうか、それも不明である。>

「前流行」の直前、1918年9月に、原敬が「平民宰相」として日本初の本格的政党内閣を組織します。有名な『原敬日記』(福村出版)には次の記述が見られます。
<午前腰越(原の別荘・引用者註)より帰京、風邪は近来各地に伝播せし流行感冒(俗に西班牙(スペイン)風と云ふ)なりしが、二日間斗りにて下熱し、昨夜は全く平熱となりたければ今朝帰京せしなり>(1918年10月29日)
どこまで事態を重く受け止めていたか、定かではありません。
欧米の大流行から4ヵ月ほどたった10月から、本格的な流行が始まります。感染はほぼ3週間で全国的に広がります。各地の学校、工場、軍隊、医療現場、火葬場などの大混乱を本書は微細に伝えます。
12月に入り、いったん小康状態を得たかに見えますが、1月に入り、死者が増えます。
<こういった事態に、東京府、東京市は何もしなかったのか。何をすべきか分からなかった、というのが実相であろう。二月五日には市長が告諭を発し、室内や身体の清潔維持、人混みを避けること、うがいの励行、患者の隔離を奨励している。(略)しかし日本では、劇場、映画館等の閉鎖は遂に行なわれなかった。>
政府はなぜもっと早く、伝染防止のために「大呉服店、学校、興行物、大工場、大展覧会等、多くの人間の密集する場所の一時的休業を命じなかったのでせうか」と、与謝野晶子が「前流行」のさなか、怒りをぶつけた論評をしています。
各種興行の閉鎖はほとんど行われず、神仏に救いを求めて殺到する満員電車の乗客には、車内での感染の危険性が高いにもかかわらず、何の規制もされませんでした。
医療体制の整っていない地方の惨状は目を覆うばかりで、福島県会津地方のある村は、
<集落(人口267人)住民全員が流行性感冒に罹り、降り続く大雪のため交通が途絶し、医師の来診も乞えず、食糧不足も起こり、病気と飢餓により、「二百余名は遂に惨死せり」という報道が遠く離れた『福岡日日新聞』や『京城日日新聞』に掲載されている(一月三〇日、三一日付)。>
こうして「前流行」は、内務省の公式統計だけでも2116.8万人の患者、25.7万人以上の死者を出し、約半年間暴れまわった後に、いずかたともなく消えてしまいます。「春の到来という季節上の変化もあったろうし、多くの人が罹患し、ウイルスへの免疫抗体を持つようになった結果かもしれない。何しろ病原体さえ分からなかった当時のことなので、予防や治療の結果でなかったことだけは確かである。(略)むしろ死亡者がこれだけで済んだのが幸運だったと考えてもいいだろう」と本書は述べます。
そして、1919(大正8)年12月から翌年5月頃にかけて「後流行」がやって来ます。当時、毎年12月1日は徴兵された新兵の入営日でしたが、そこでクラスターが生じます。免疫のない新兵たちが3密(密閉・密集・密接)環境のウイルスの渦巻く兵営に、いわば無防備のまま飛び込んでいきます。
<この軍隊における罹患こそ、本格的な「後流行」の点火剤となったのである。>
典型的な事例として、乗員469名のうち306人が感染、48人が亡くなった軍艦「矢矧(やはぎ)」の爆発的な感染拡大など、まさに「海に浮かぶ閉鎖空間」の惨状は、今回のクルーズ船を想起させる出来事です。
ただ、不幸中の幸いだったことに、本来の「矢矧」の乗組員の他に、シンガポールから日本に帰る巡洋艦「明石」の乗組員が乗り込んでいました。彼らはすでにどこかでインフルエンザに罹患して、免疫を獲得していたのです。かくして、「矢矧」の乗組員が次々に倒れてゆくなかで、彼らが航行をバックアップし、「機関停止漂泊寸前」の危機をかろうじて救うのです。

内務省の記録では、「後流行」の患者は241万人、死者は12.8万人です。「前流行」では、多数の患者が出たので、死亡率は相対的に低かった(1.22%)のですが、「後流行」では、患者は少なかった(「前流行」の1割程度。多くの人が免疫を得ていた)のですが、そのうち5%が亡くなり、死亡率は4倍以上に跳ね上がります。「各地で棺桶が払底し、茶箱を用いるところも出てきた」と。
内務省の数字では、全流行期間の患者は約2358万人、死者は38.5万人とされますが、速水さんはこの見積もりは過小だと考え、死者を45.3万人と試算します。先述した通りです。
日本におけるスペイン・インフルエンザは、1918年5月から1920年5月頃まで、約2年間続きました。いったん収束しても、第2波、第3波がやって来ました。抗体ができれば罹患率は下がりますが、ウイルスの変異で毒性が高まる可能性もあります。ワクチンの開発が待たれるわけです。
ともかく100年前と現在では単純な比較はできませんが、それでも貴重な「教訓」が含まれていることは確かです。となると、これほどまでに凄まじい人的損失をもたらした事件が、なぜ忘れ去られてしまったのか?
ことは日本に限った話ではありません。名著『史上最悪のインフルエンザ』(アルフレッド・クロスビー、みすず書房)の中で、アメリカの歴史学者は「なぜ忘却されたか?」の理由として、次の4点を挙げています。
・第一次世界大戦に対する関心が、スペイン・インフルエンザより勝っていた。
・スペイン・インフルエンザによる死亡率は、高いとは言えなかった。
・スペイン・インフルエンザは突然やってきて、人々をなぎ倒しはしたが、あっという間に去り、戻ってこなかった。
・スペイン・インフルエンザは、超有名な人物の命を奪わなかった。
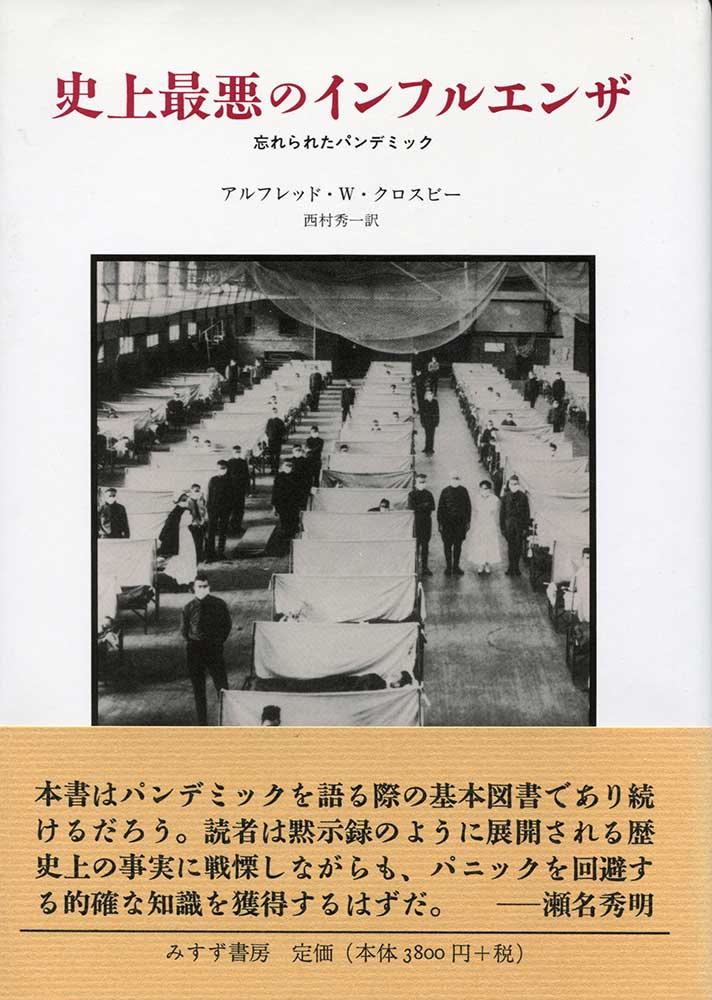
最後の点、日本では劇作家・演出家として活躍した島村抱月が、1918年10月末の「前流行」の時期に罹患し、11月5日に死去しています。「抱月が育て、恋愛問題にまで発展した」女優・松井須磨子が、翌年1月に後追い自殺したことで、スペイン・インフルエンザといえば、必ずこの悲劇が語られます。
日本で忘れられた最大の理由は、スペイン・インフルエンザが終息した5年後に、関東大震災が起きたせいでしょう。東京・横浜を灰燼に帰した大震災です。死者は約10万人と、スペイン・インフルエンザの45万人余の4分の1ですが、関東大震災は首都圏に焼野原を作り出しました。スペイン・インフルエンザが記憶に刻まれなかったのは、日本の景観を変えなかったせいではないか、と速水さんは興味深い指摘をします。

<本書を記すにあたって、スペイン・インフルエンザ流行期の写真を探したが、ほとんど見つからなかったのも、スペイン・インフルエンザが「絵にならなかった」からであろう。
ともかく関東大震災の一撃によって、スペイン・インフルエンザは記憶の片隅に追いやられてしまった。さらに、昭和期に入ると、日中戦争、太平洋戦争とスペイン・インフルエンザより、もう一桁多い戦死者や一般市民の犠牲者を出す出来事があいつぎ、その思い出は忘却のなかに薄らいでしまった。>
そして速水さんは、本書全体をこう締め括ります。
<結論的にいえば、日本はスペイン・インフルエンザの災禍からほとんど何も学ばず、あたら四五万人の生命を無駄にした。「天災」のように将来やって来る新型インフルエンザや疫病の大流行に際しては、医学上はもちろん、嵐のもとでの市民生活の維持に、何が最も不可欠かを見定めることが何より必要である。つまり、スペイン・インフルエンザから何も学んでこなかったこと自体を教訓とし、過去の被害の実際を知り、人々がその時の「新型インフルエンザ・ウイルス」にどう対したかを知ることから始めなければならない。>
なぜなら――と述べる理由は、かつて直接聞いた言葉です。
<人類とウイルス、とくにインフルエンザ・ウイルスとの戦いは両者が存在する限り永久に繰り返されるからである。>

2020年4月23日
ほぼ日の学校長













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。