ほぼ日の学校長だよりNo.89
「よみがえった写真――藤原審爾さんのこと」
幕張メッセで行われた、矢沢永吉さんプロデュースのロックフェス「ONE NIGHT SHOW 2019」に糸井さんらが行って、永ちゃんの凄まじいパワーに感動していたのと同じ日に、私は友人のほとんど強制的な「オススメ」にしたがって、サントリーホールに向かいました。
倍賞千恵子さんが贈る「バースデイコンサート2019 with 小六禮次郎(ころくれいじろう)」を聴くためです。永ちゃんが1949年9月14日生まれの70歳間近なら(とてもそうは見えませんが)、倍賞さんは1941年6月29日生まれの78歳。

「チコちゃん」と呼ばれて童謡を歌っていた少女時代から、松竹音楽舞踊学校を首席で卒業し、松竹歌劇団(SKD)に入団。ほどなく松竹にスカウトされて女優デビュー。そして翌年、「下町の太陽」で歌手デビューし、それが映画化されて大ヒット‥‥という個人芸能史を振り返りながら、なごやかで親密なひと時をプレゼントしてくれました。
ピアノ伴奏したご主人の小六禮次郎さんとのユーモラスな掛け合いも微笑ましく、懐かしい昭和の歌の数々がしっとり心に沁みわたります。過ぎし日をかみしめながら、なお凛(りん)として響く澄んだ歌声は、聴く者の目をうるませるものがありました。
これまで出演した映画作品は174本(!)で、12月27日に公開される寅さんシリーズ「男はつらいよ お帰り寅さん」(1969年の第1作からちょうど50年目の第50作。シリーズ前作からは22年ぶり)が175本目になるのだとか。
そんな話を聞いていると、初めて倍賞さんにお会いした日のことを思い出します。おそらく1979年か80年の12月27日。毎月27日に開かれていたある私的な勉強会でのことでした。
藤原審爾(ふじわらしんじ)といっても、もう知る人はほとんどいないかもしれません。戦後間もなく清冽な叙情みなぎる恋愛小説「秋津温泉」(『秋津温泉』集英社文庫所収)で注目を浴び、その後は純文学からさまざまなエンタテインメント作品まで幅広く手がけた作家です。会った人をふわりと包み込むような、やわらかな笑顔が魅力的でした。

1984年12月20日に63歳で亡くなります。自宅でとりおこなわれた密葬には、故人を偲ぶ多数の人たちが参列し、各紙誌に追悼文が掲載されました。なかでも忘れられないのは、「同型の先輩としてその一挙一動を見習った」といって、死の衝撃に呆然と立ちすくんでいた色川武大(たけひろ)さんの姿です。
<ぼくだって、不摂生で身体はめちゃくちゃで、五十歩百歩、すぐにそちらに追いかけていくような気もしますが、こうなったら、なんとか一日でも長くがんばって、藤原さんの代役を、およばずながらこの世で果たしたいと思います。ぼくは藤原さんが手塩にかけて育ててくれた第一号ですからね。>(色川武大「藤原審爾さん」、『色川武大・阿佐田哲也ベスト・エッセイ』ちくま文庫所収)
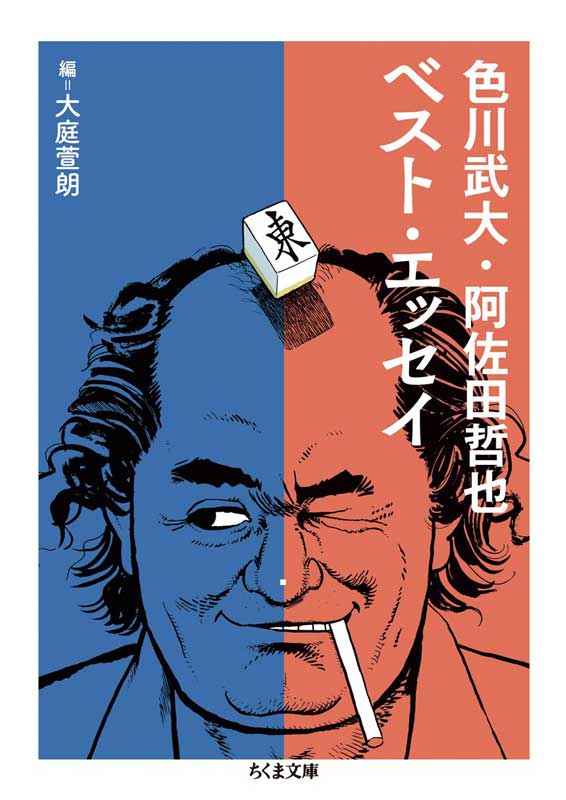
藤原さんの話はまたあとで触れるとして、倍賞さんと初めてお会いした日のことです。それは、藤原さんが毎月27日に自宅の居間を使って、各出版社の編集者や作家、ライターなどを集めて開いていた俗称“藤原学校”こと「27日会」という勉強会でした。
私は編集者になって2年目の秋から、この会に加わりました。ふだんは毎回テーマを決めて、誰か適当な講師を招き、短い講話のあとの質疑応答の半ばから、藤原家手づくりの美味しい夕食をともにしながら、談論風発をたのしむといった会でした。
ただ、暮れの27日だけは「勉強」のほうはお休みにして、クリスマス・パーティを兼ねた忘年会になりました。ひとり3000円以下で思い思いのプレゼントを用意し、あみだくじで福引をやります。藤原さんからは備前焼の食器、酒器、花器、まれには大きな傘立てまでが提供されました。
その日も大いに盛り上がったと思います。常連の江國滋さん(江國香織さんのお父さん)、画家の堀文子さんらがいらっしゃいました。ふだん欠席がちの倍賞さん、山田洋次監督も参加しました。
その日が初対面だった倍賞さんは、私の左隣の席でした。食べ物の話や、藤原さんのことなど、気軽な話題をずっとしゃべっていたような気がします。どういう話の流れだったか、倍賞さんが使っていたフェルト製のライター入れを私が貰い受けることになりました。
可愛らしい、100円ライターを入れるのに手頃な袋でした。当時、ほんのわずかの間、喫煙者だった私は、しばらく愛用させていただきました。その後、しばらくはデスクの引出しにありましたが、いつの間にか姿を消してしまいます。
この27日会を主催していた藤原さんは、「寝るヒマがあるくらいなら、勉強しなよ」が口癖でした。「勉強」の幅はひろく、人生全般が対象です。藤原さんは、「旦那芸としては玄人に近いレベル」(色川武大)と評される麻雀も凄腕なら、何事につけ凝り性で、野球、釣り、陶芸なども徹底しなければ気が済まない人でした。
「とにかくやさしい人だ。やさしい親分、生まれついてのね。金をふんだんに遣う。それも人のために遣う。だから仕事が忙しくなる」(安岡章太郎)という人でもありました。
<藤原さんは人を集めるのが大好きだった。後年まで同人誌を応援したり、自宅に文学塾を作って毎週講義したり、編集者たちとの旅行会、十七日会、二十七日会などの勉強会、それから野球チームを作って文学青年でない若い人たちとの接触を計ったり、晩年の『死にたがる子』にからむ全国の母親たちとの交流など、そうして自身も意外に勉強家、努力家だった。
ところが、そうばかりかと思うと、若い頃からの無頼な面がずっと同居していて、そこがまた魅力の一面にもなっていた。私がぞっこんほれこんで藤原さんのあとばかりくっついていた頃、出版社が罐詰にした旅館の隣りの部屋に、藤原さんが自費で部屋をもう一つとって、
「色ちゃん、どうせならここで君も仕事をしなよ」
それで朝起きると花札をやったり、街にビンゴをしに行ったり、結局二人とも仕事をしないで遊び呆けてしまう。夜になって、
「明日は、まじめに仕事しような」
などと反省するけれども、やっぱりビンゴ。それでも一人になりたがらない。肉親の縁にうすい人特有の淋しがり屋だった。>(色川武大「回想」、『小説新潮』1985年3月号「追悼 藤原審爾」)
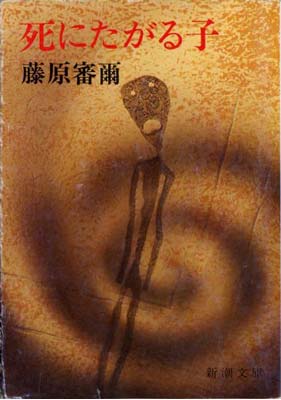
「毎日寝るなんて贅沢だよ、寝るのは一日おきくらいでちょうどいい」と、色川さんには言ったそうです。丈夫な人なのか、といえば、とんでもない。若い時から大病(肺結核)をわずらい、片肺と肋骨を切除し、その後も胆嚢を取り、心臓、肝臓、膵臓、腎臓、それから糖尿病、ジフテリアだの腸チフスだの、数えきれないほどの病気を背負っていました。
色川さんにいわせれば、「病気の問屋」みたいな人です。病弱の人は摂生するから長生きするといわれますが、藤原さんは病気のうえに不摂生で、それで人一倍仕事をします。文士という言葉が似つかわしい無頼な一面と、努力家、勉強家で意志的な一面とが同居していて、それが独特の魅力でした。
どう頑張って言葉を費やしても、あの「大きな人柄を、今、そっくり字にできないのが残念だ」と色川さんは書いています。藤原さんの多彩な表情のすべては到底つかみきれません。ただ、いま蘇ってくるのは、27日会が行われていた居間にあった写真です。藤原さんの定位置のちょうど真後ろあたりに置かれていました。
誰かにもらったものだとおっしゃっていましたが、おそらくは終戦直後の撮影だと思います。山深い分教場(?)の教室で、数人の児童が教科書を受け取っているスナップです。「この目を見てよ」と、藤原さんは言いました。子どもたちの嬉しそうな、キラキラした目がありました。
ある時、仲間の編集者の話題になりました。誰かが彼のことを、からかい半分に噂のネタにしたのです。すると、何を思ったか、藤原さんが「あいつの小学校の担任というのは、新婚間もない先生だったらしい。どこかの二階に間借りしていて、そこん家(ち)に子どもたちが遊びに行く。調子に乗ってドカドカ土足で上がっていく子がいる。なのに、先生も新婚の奥さんも、いつも嬉しそうに迎えて、いやな顔ひとつしなかったというんだな。そういう先生を見てきたあいつは、人の何が大事か、ちゃんとわかってる。だから大丈夫なんだ」という話をしました。
藤原さんの死後に刊行された『遺す言葉』(新潮社)という本の冒頭に出てくるエピソードを思い出します。広津和郎(ひろつかずお、1891―1968)という藤原さんが師とあおぎ、その死にあっては葬儀委員長をつとめた作家の言葉です。広津和郎は、先輩作家である徳田秋声(とくだしゅうせい、1872―1943)について、こう言ったそうです。
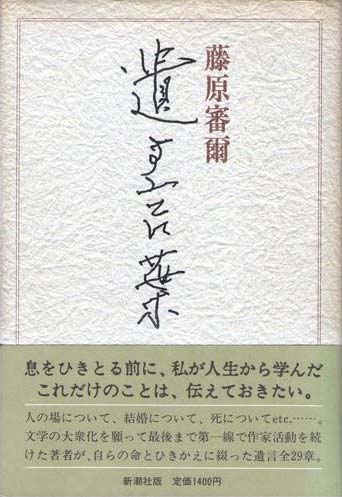
「徳田秋声という男は、親子関係をみても、女や金の面をみても、乙をつけられるところはないね。どの面をみても、丙しかつけられない男だったが、しかしそういうところを全部ひっくるめた徳田秋声というのは、甲上の人物だったね」
甲乙丙(こうおつへい)というのは、いまでいうならABCの3段階評価です。つまり、人を評価する際には、欠点を一つ、二つ個別にあげつらうのではなく、全体をもっと総合的に見なさい、ということでしょう。この話は何度も、藤原さんからじかに聞きました。
この『遺す言葉』には巻末に「編集部付記」があり、出版にいたるまでの経緯が述べられています。
<本篇は「波」昭和五十年八月号から五十二年十二月号まで連載された。当初、著者は数種の病を併発して、ことのほか身体不調のなかにあった。「はじめの言葉」にあるように、世に遺った言葉や、著者自らが苦闘の人生に学んだ教訓のなかから、これだけは後世の人に伝えておきたいという強い念願が執筆の動機となったのである。二年半二十九回、一度の休載もなしに筆は運ばれ、「死について」で完結を見た。その後、単行本上梓にあたっての補筆を得ぬまま数年が過ぎたが、そろそろ本篇の仕上げにかかりたいと著者から申し出があったその矢先に、肝硬変の疑いで入院が決定、二ヵ月もたたぬ昭和五十九年十二月二十日、帰らぬ人となった。享年六十三歳。文字通り本書が、『遺す言葉』――遺言の書となった所以である。>
27日会の先輩で、講談社の名物編集長だった大村彦次郎さんが、「教育者」としての藤原さんの横顔を次のように書いています。
<藤原さんは裕福な環境に生まれたが、肉親の縁薄く、祖母に育てられる、という孤児のような少年時代を過した。そのせいか人なつこく、まわりに若い作家や編集者をよく集めた。地主の旦那が小作人の子弟を教導するかのように、ちょっとお説教を垂れるようなおもむきがあった。社会の仕組みや人生の真善美について語るのが好きで、それも論理でなく、独特の感性で裏づけていたから、藤原さんの気質や発想を理解しないと、わかりづらいところもあった。(略)
晩年になってからも、藤原さんは書くだけではなく、地方の高校や婦人団体から講演を頼まれると、よく出かけていった。講演料は受けとらず、主催者側に寄付した。松川事件の広津和郎が、事件に関する原稿料や講演料のすべてを、仙台の拘置所にいる被告団に、薬代として送っていた範にならったのである。>(大村彦次郎『文壇うたかた物語』、ちくま文庫)

先週はたまたま「学ぶ」ことについて対談をしたり、「ほぼ日の学校」の話をしながら、「学ぶことのたのしさ」とは何かを、いろいろな人たちと一緒に考える時間が続きました。
そんな時間の流れに身を置いているさなか、藤原さんの居間に飾られていた写真が蘇ってきました。真新しい教科書を受け取る子どもたちの晴れがましく、嬉しそうな表情が目に浮かびます。手渡す先生の姿もあったはずです。藤原さんは、「何かを思い出さないか?」と尋ねた気がします。
写真のことは、ずっと忘れたままでした。倍賞さんのコンサートに行ったおかげで、それが“奇跡のように”蘇ってきました。答えを全部いうのではなくて、考えさせるヒントをのこす――それが「教育者」藤原審爾のスタイルだった気がします。
<暮れに、病室で、ラークしか吸わない藤原さんが、不意にぼくの煙草に手を伸ばして、一本とって火をつけた。そのときぼくはうっかりして深く考えなかったが、それが藤原さんらしい藤原さんと会った最後の日だった。>(色川武大「お別れの煙草」、毎日新聞夕刊)
病室で「君の煙草がほしい」といわれ、それをうまそうに喫っている藤原さんの姿を見たのは、安岡章太郎さんも同じです。
久々に手にとった『遺す言葉』から、好きな一節を引いて締めくくりたいと思います。
<あるときわたしは、裏山で野苺(のいちご)のみごとな群れをみつけ、それを摘み、竹籠に入れて戻り、独りでたべていたところを、祖母にみつかり、つよくとがめられたことがある。皆にわけて一緒にたべなさいというのである。わたしは山でそれをみつけ、独りで摘んで戻ったのであるから、その努力にたいして応分の配慮があって然るべきだという思いを拭いがたく、いささか不満であった。
その不満に答えて、祖母は、山の幸は万民のものだと説き、一人はうまからずということばを、人としての心の持ちかたを、わたしに教えた。その折また祖母は、一人はうまからずということばのことを、「これは、世に遺った言葉ですよ」と言った。
ことばにもそのつかいようにも、この世に生きた人々の願望理想がこもっており、そういうふくらみへの感応が、時に人にペンをとらせるというようなことをさせる場合もあるのではないだろうか。強いて申さば、いまのわたし、その一人である。>(「はじめの言葉」より)
2019年7月11日
ほぼ日の学校長













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。