ほぼ日の学校長だよりNo.114
読んでた本が悪いのか?
それは先週金曜日、24時をわずかにまわった頃でした。
終電に駆け込もうとバタバタ仕事を切り上げて、バッグに読書用のメガネや何やら、七つ道具をしまいこんでいた時です。
「あれッ? ない!」。体が凍(こお)りつきました。
財布と名刺入れの入った黒い小物入れが、バッグの中にありません!
そ、そんな、バカな‥‥
あたりを探しますが、見当たりません。
終電をあきらめ、捜索開始。その夜の行動をトレースし、落とした(あるいは忘れた)とおぼしき場所を思い浮かべます。
最後にお金を払ったのは、オフィスのすぐ近くのマーケット。レシートにある番号に電話をします。幸い、人が残っていました。「そろそろ終電なので‥‥」と言いながらも、丁寧に応対してくれます。でも、ほんとに申し訳なさそうに「どうも届いていないみたいです」と。
タクシーの領収書をポケットから取り出し、タクシー会社に電話します。車番を伝え、ドライバーに連絡を取ってもらいます。本人と連絡がつき次第、折り返します、と。

次に、タクシーに乗る前に、会食をした広尾のお店。そこを出る時、店長と名刺交換したのは覚えています。小物入れから名刺入れを取り出したのは確かです。
店に電話しましたが、あいにく留守番電話の応答です。営業時間が終了したこと、土日は休みだということを告げられます。このお店に忘れた可能性はまずないだろう、と感じます。
となると、やはりタクシーだろうかと思いながら、ともかくカード会社に連絡します。なかなか電話が繋がらず、イライラしながらの10数分。とりあえず止めてもらうように伝えます。10時半以降に使われた形跡はまだない、と。それを聞いて、ひと安心。
前に、同じ会社の先輩が、お通夜の席で“香典泥棒”にハンドバッグを盗まれて、あっという間に高額商品をカードでまとめ買いされる被害に遭いました。
タクシー会社に再度TEL。「実車中なので、まだ連絡がつきません」。深夜の遠距離。タクシーにとっては上客だな‥‥八王子あたりだろうか、などと、どうでもいいことを考えます。
買い物は小銭入れで払った気がするし、やっぱりタクシーだな、と思えてきます。車中、本を読もうとして、読書用のメガネに替えたりしたので、降りる段になって、手もとがバタついた気がしてきます。支払いを済ませ、財布を小物入れにしまったところで、そのまま置き忘れてきたような絵が浮かびます。
すると、タクシー会社から、待ちかねていた電話。「見当たらない」と、つれない報告。ガーン!
約1時間半が経過しました。もはや覚悟を決めたほうがいいかもしれない‥‥。
ネットで調べて最寄りの警察署に連絡し、遺失物の届け出をしたいと伝えます。名前と紛失物、紛失した想定時刻と場所を尋ねられ、元気なく答えます。しばらくすると、なんとも穏やかな、落ち着いた口調で告げられます。「そのお名前で、隣の署に届け出があったみたいです」。
えッ! なぜか、そういう期待はいっさい抱いていなかったのです。
さっそくその署に電話すると、保管している派出所を教えてくれました。ともかく大急ぎで駆けつけました。

そして午前2時半、感激の“再会”を果たします。そのままの姿で戻ってきました。
道で拾ったと、男性が届けてくれたそうです。「名前も伝えなくて結構です。御礼も要りません」と言って、立ち去ったとか。
拾った場所から交番までは、けっこう距離があるのです。わざわざ届けてくれたのでしょう。
こういうドジは、忙しい時に限ってやるものです。以前、買ったばかりの6ヵ月の定期券を落とした際も(これは出てきませんでしたが)、目がまわるほど忙しいさなかのことでした。“厄落とし”だと、すっぱり思い切りましたが。
さて、帰宅しようと派出所前でタクシーを拾います。走り出したところで、「何かあったんですか?」と運転手さん。「実は、財布を落としちゃってね。見つかったんだけど」
いきなり運転手さんが、振り向きます。「いや、私も1週間前に財布を落としまして!」
「ちょっと、危ない! 前見て走ってよ!」
「は、はい」
「これで交通事故に遭ったら、今晩2度ババを引くことになる」
「出てこないんです、私のほうは。運転免許証が入ってたんで、大変でした」
そこから、長い話が始まりました。
「お客さん、現金はいくらぐらい入れてました?」
「*万円くらい」
「私と一緒だ」
また振り返ろうとするので、押しとどめます。
「現金は、いいです。あきらめます。でも免許証でしょ。健康保険証、クレジットカード、キャッシュカード、診察券‥‥あらゆるものが入ってたんで、この1週間、タイヘンでした」。
道中、ずっとこの話が続きました。
それにしても、どうして道に落としたんだろう? 会食先からタクシーで戻ってきて、下車した時に落としたのか‥‥。気がつかなかったのが不思議です。
帰宅後あれこれ考えながら、ウイスキーを生(き)で飲みます。タクシーで読みかけていた本をバッグの中から取り出します。そうか、こいつを夢中で読んでいたんだ! 20数年ぶりに読み返した本。つい没入してしまったのです。

中島らも『今夜、すべてのバーで』(講談社文庫)――。
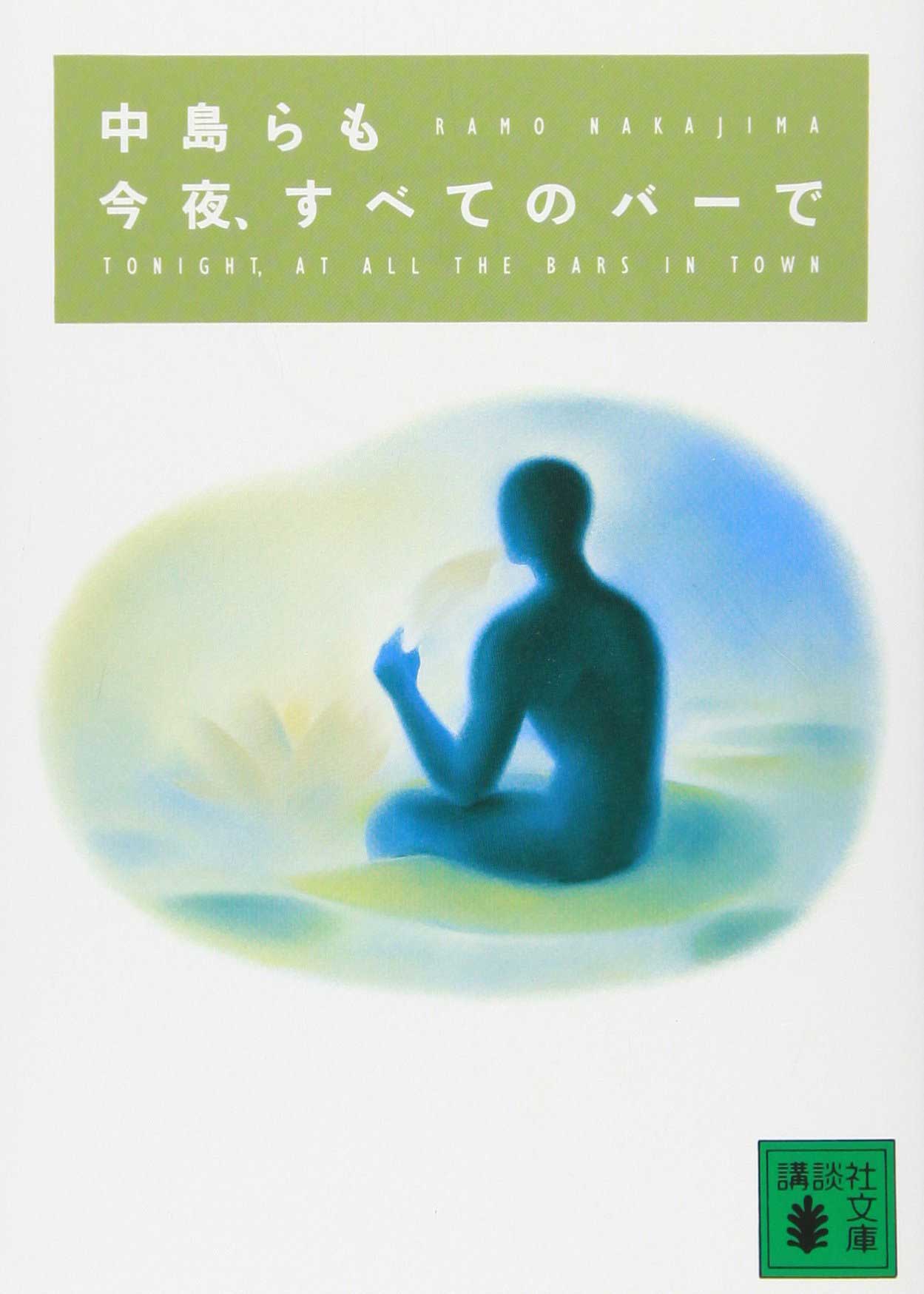
著者の実体験をもとにした、アルコール依存症患者の壮絶な闘病小説です。笑いのセンスが秀逸で、さりげない台詞が決まっています。35歳の主人公と入院先の担当医とのハードボイルドなやりとりは、テンポが良くて絶品です。
主人公は3人の人間から、“35歳で死ぬ”ことを宣告されます。そのまさに予言の年に、「生きてるのが不思議なくらいの」γ(ガンマ)GTP1300の状態で入院します。
18の年から17年間、毎日ウイスキーを1本ずつ飲み続けたという、「それなりに破れかぶれの、密度のある人生」の到達点です。
<「三十五歳死亡説」のご託宣(たくせん)をたまわってから、おれは自分なりには「アル中」に対してのアンテナを張ってきた。(略)おそらくは、アル中になっていく段階で、おれほどアル中の実態をつかんでいた人間というのは、あまりいないのではないだろうか。
そして結局のところ、そうした医学的知識や、精神病理学的知識は、おれにとっては何の役にも立たなかったことになる。
おれがアル中の資料をむさぼるように読んだのは結局のところ、「まだ飲める」ことを確認するためだった。>
<今日しなくてはいけないことは明日する。今日飲める酒も明日の分の酒も今日のうちに飲んでしまおう。それがおれの選択だった。>
アル中についての知識がハンパでない主人公にあきれはて、担当医の赤河は、プレスリーもブライアン・ジョーンズも、ジミ・ヘンドリックスも、ジム・モリスンも、「みんなみんな、アルコールとドラッグで死んでいったんだ。そうだろ?」と、主人公の顔を見据えます。
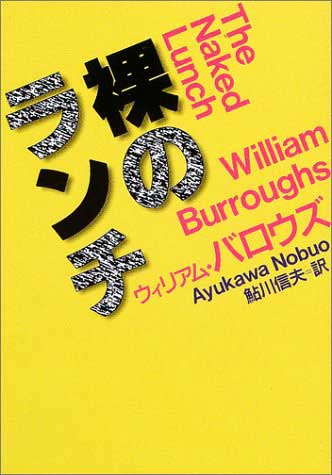
中島らもさんが敬愛した作家ウィリアム・バロウズが、ジャンキー時代に書いた名作『裸のランチ』(河出文庫)。「書いたことさえ覚えていないと告白している」と。
<「そうやって死ぬとこまでまねしたいんだろ。え? ジアゼパムだ」
赤河はおれの腕にぷすっと注射器を突き立てて、ジアゼパムを注射した。
「さ、これがニトラゼパムの錠剤だ。飲めよ、ほら。水で飲めないなら、ビール出してやろうか?」
おれは、出されたクスリを、看護婦の差し出してくれた水で飲み込んだ。
「じゃあな、勉強家のアル中さんよ。よく眠るんだな」
おれは感情をひとたらしもこぼすまいと、ゆっくり立ち上がり、礼をした。
「ありがとうございました」
「それでもまだ手がふるえるようだったら、マンドリンを貸してやるよ」
「マンドリン?」
「ああ。アル中にはマンドリンが一番なんだ。手がふるえて、いいトレモロが弾けるからな」>
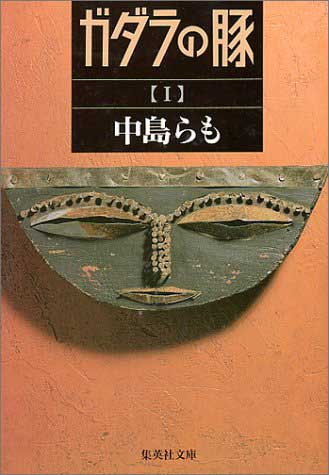
この二人がクライマックスに、病院の霊安室の遺体の脇で、薬用のエチルアルコールをビ―カーで酌み交わし、殴り合う場面は圧巻です。すでに一度は読んでいるにもかかわらず、早くそこにたどり着きたくて、夢中でページを繰っていたのです。
<深夜の静まり返ったロビーを、音をたてずに通り抜けようとすると、
「午前さまか」
と聞き慣れた声がした。
ロビーの中央あたりの長椅子に、黒い人影がどっかりと腰をおろしていた。そいつはゆっくり立ち上がると、長身をおれの方へ向けて運んできた。
「どうだい。街は楽しかったかい。田舎町にしちゃ、けっこういいスナックがあっただろう」>

ここから始まる13ページ。赤河医師の言葉の連打が、重いボディーブローのように効いてきます。
<「なおる奴もいりゃ、死んでく奴もいたよ。私は、なんとか助けてやりたいと思った。ことに子供の患者はな。そうだろ? 子供なんてのは、人生の中で一番つまらないことをさせられてるんだからな。私だって十七までに面白いことなんか何ひとつなかった。面白いのは大人になってからだ。ほんとに怒るのも、ほんとに笑うのも、大人にしかできないことだ。なぜなら、大人にならないと、ものごとは見えないからだ。小学生には、壁の棚の上に何がのっかってるかなんて見えないじゃないか。そうだろ?」
「そうですね」
「一センチのびていくごとにものが見えだして、風景のほんとの意味がわかってくるんだ。そうだろ?」
「そうです」
「なのに、なんで子供のうちに死ななくちゃならんのだ。つまらない勉強ばっかりさせられて、嘘っぱちの行儀や礼儀を教えられて。大人にならずに死ぬなんて、つまらんじゃないか。せめて恋人を抱いて、もうこのまま死んでもかまわないっていうような夜があって。天の一番高い所からこの世を見おろすような一夜があって。死ぬならそれからでいいじゃないか。そうだろ。ちがうかい?」
「いや、その通りです」
「私はな、なんとか助けてやりたいと思ったよ。子供をね。でも、そのうち、それも思い上がりだってことに気がついた」>
まだまだ、赤河の名言が続きます。
「医者というのは、たとえば駅へ行きたい人に道を教えてあげる煙草屋のおばさん。そんなようなもんでしかない。歩いて駅まで行くのはその人だ。煙草屋のおばさんが背負って走るわけにはいかんからな」
「問題は、患者が、前へ進むことだ。だから、助けてやりたい、なんてことはこんりんざい思わないようにした。助かろうとする意志をもって、人間が前へ進んでくれればそれでいいんだ」
『今夜、すべてのバーで』を最初に教えてくれた人は、一晩中、その話だけをしながら飲んでいました。本を読んだ私と、次には感想戦をやりながら飲みました。その後もしばらくは、この小説を肴にしながら、飲み続けました。不思議に思い出深い作品です。
読み返してみると、最後に引用したドクター赤河のセリフなどは、むしろ20数年たったいまこそ、身にしみます。いったいこの20数年間、おれは何をしてきたんだろう、とまるで酔っ払いが考えそうな想念にひたって、最後の1行までを読み尽くしました。
この本を読み始めたことが、先週金曜日の失敗でした。タクシーでも電車でも、読む本は選ばなくてはいけません。
さて間もなく2月22日から3日間、渋谷PARCOの8Fで「本屋さん、あつまる。」というイベントを行います。その本屋さんのひとつとして、私が店主を務める「河野書店」も出店します。とっておきの選書をして、平台に22冊を並べるつもりです。
もちろん、『今夜、すべてのバーで』も、そこに欠かせない1冊です。
2020年2月20日
ほぼ日の学校長
*来週は1回休みます。次の配信は3月5日の予定です。
*2/22(土)〜24(月・祝)まで、渋谷PARCO8階の「ほぼ日曜日」でほぼ日の学校主催のイベント「本屋さん、あつまる。」を行います。8店舗のおもしろくてワクワクする選書の本屋さんが大集合! 毎日トークイベントも行われますので、ぜひ遊びに来てください!ゆっくり過ごしていただけるよう、お酒もご用意してお待ちしています!
詳しくはこちらをごらんください。














メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。