ほぼ日の学校長だよりNo.64
「“予習茶話会”始め」
2019年の「ほぼ日の学校」は、1月16日の岡野弘彦さんの講義から始まります。「万葉集」講座の第3回。大伴家持(おおとものやかもち)についてお話しいただきます。
そこに、思いがけない出来事がありました。元日の朝日新聞が1面トップで、「昭和天皇 直筆原稿見つかる/晩年の歌252首 推敲の跡も」という特ダネ記事を掲載したのです。「昭和天皇の歌の晩年の相談役で直筆を見たことのある歌人」として、岡野さんが紹介され、「筆跡と内容」を確認しておられます。
さらに1月7日にも「昭和天皇 和歌磨いた跡/侍従長『清書』に歌人の助言」という続報(同紙1面トップ)が掲載されます。「昭和天皇が心に浮かんだことをまずメモに書き留め、それを罫紙で推敲、側近が清書して相談役の助言を受けて完成させる――という歌づくりの流れ」があったそうで、この相談役が岡野さんです。
前から講師をお願いしていた岡野さんが、いきなり「時の人」になったわけで、こいつぁ春から縁起がいいわい、かどうか、なんだか落ち着かない気分になっています。
ともあれ、1月16日の講義に先立って、11日に「予習茶話会」を行う旨は、12月の段階で受講生には伝えてあります。せっかくの岡野先生の授業なので、事前に先生のご紹介をしておいたほうがよいのではないか――。学校スタッフの発案で、私が“勉強会”を主宰することになったのです。
岡野先生には、ちょうど私が編集者になりたての頃、雑誌「中央公論」で11年間にわたって「短歌の風土」という連載をお書きいただきました。自分自身が担当だったわけではありませんが、毎月編集部員として真っ先に読ませていただきました。にもかかわらず、歌心が一向に芽ぶいてこなかったのはどうしてなのか? なんだか申し訳ないような気持ちでおります。
10年前に59歳で亡くなった作家の海老沢泰久(えびさわやすひさ)さんは、岡野先生の国学院大学での教え子でした。私は、海老沢さんが監督をしていたサッカーチームに誘われ、何シーズンか、チームの一員として都内のリーグ戦に参加しました。毎年暮れの納会の季節になると、必ず海老沢さんが言いました。「師走の20日から1週間は、岡野先生たちと万葉旅行に出かけるので、その時期を外してほしい」と。
これは国文学者の折口信夫(おりぐちしのぶ)博士を記念した、国学院大学の古代研究所の恒例行事として、1964年から続いている飛鳥万葉の旅でした。海老沢さんがことのほか重視していることは、言葉の端々から伝わりました。
1年間、毎週2時間半を費やして、しっかり学んだ万葉集の歌とそのゆかりの地を、できるだけ乗り物を使わずに、足で一歩一歩まわって体感しようという旅です。東京を夜行列車で出発し、現地ではひたすら万葉人のように歩く。これが実に楽しいのだと、海老沢さんは語ってくれました。
海老沢さんといえば、プロ野球ヤクルトスワローズを初優勝(1979年)に導いた広岡達朗氏をモデルにした小説『監督』で本格デビューし、その頃はホンダF1チームを描いた『F1地上の夢』などを書いていました。折口信夫、古代研究所、万葉集というのは海老沢さんのまったく意外な一面であり、この旅の話はずっと心に残っていました。
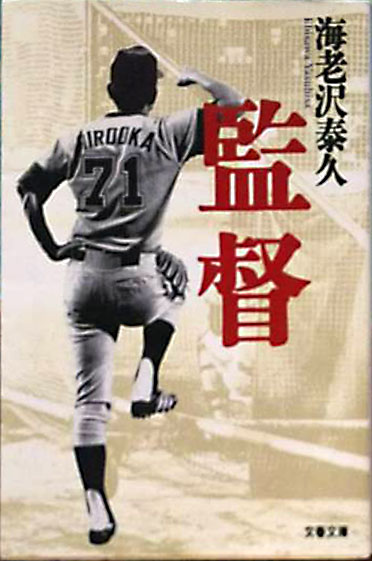
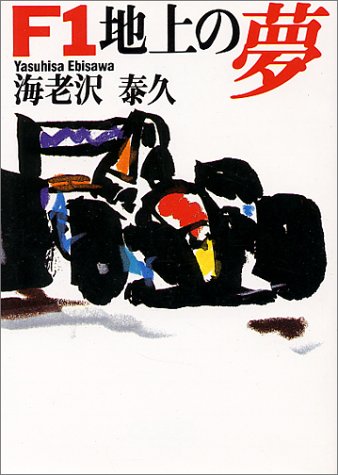
海老沢さんが亡くなった時、岡野さんが葬儀でお詠みになった歌が3首あります。
魂(たま)まつる盆の夕べぞ。男(を)ざかりの命尽くして 君すでになし
われよりも早く逝きたる君を哭(な)く。夜声の蟬の生き弱るまで
秋風の大和のむらを行きゆかば、うら若き日の 君に逢はむか
先ほど名前をあげた折口信夫(1887~1953)という人は、歌人・釋迢空(しゃくちょうくう)の名でも活躍した国文学者です。柳田国男の影響を受け、民俗学を導入した国文学研究を展開し、国学院大学や慶應義塾大学で教鞭を取りました。岡野さんは1947年から1953年に折口が永眠するまで、足かけ7年、最後の内弟子として折口の家で起居をともにしながら、20代の時を過ごします。昔ふうにいえば、書生です。

『折口信夫の記』、『折口信夫伝』(ともに中央公論新社)、『折口信夫の晩年』(中央公論社、のち中公文庫、慶應義塾大学出版会)などの著作があります。折口の没後すぐに刊行が始まった『折口信夫全集』(中央公論社)の編集にたずさわった岡野さんのことを、私は中央公論社の先輩たちから聞いていました。
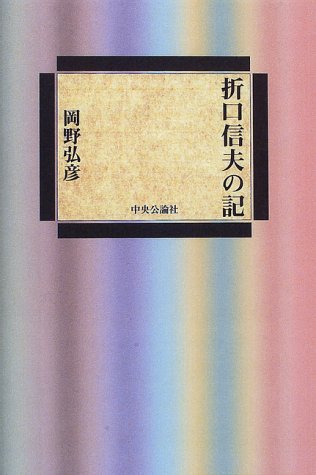
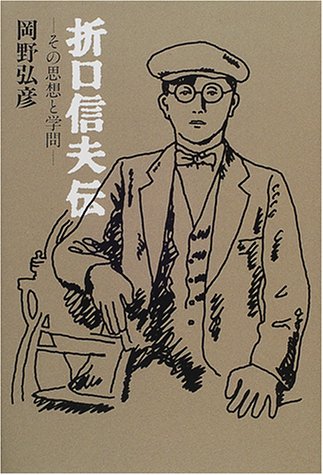
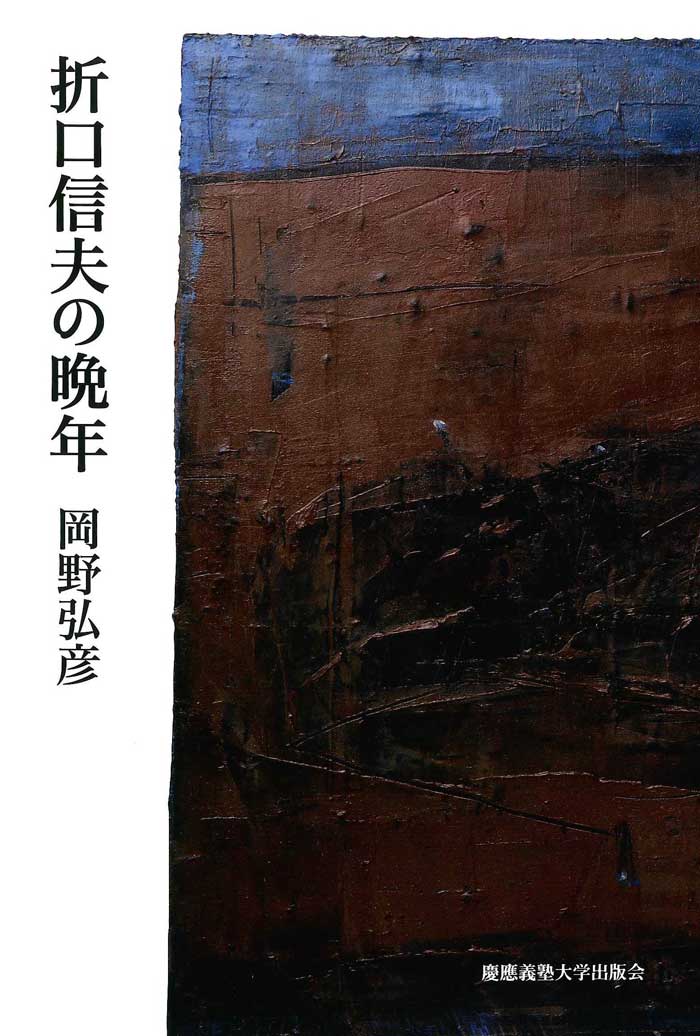
岡野さんのご実家は、伊勢と大和の国境(くにざかい)の深い山奥にあります。川上山若宮八幡宮の世襲の社家の長男として、1924年に生まれます。折口信夫の逝去が1953年9月3日。29歳の岡野さんは、その年末に家職の35代神主を弟に継がせることを父に願い出て、自らは東京にとどまり『折口信夫全集』の編集に従事します。
執(しふ)深く生きよと我にのらせしは息とだえます三日前のこと
「全集」発刊のいきさつは、中央公論社の編集者の回想録に、次のように書かれています。
<彼の死後、当然にその全集刊行が話題となり、彼の門下生の主宰する出版社が、これまた当然に出版するものと考えていたある日、私が今泉篤男、土方定一、河北倫明の諸氏と会合している席上に折口家から突然に電話があって、折口門下の長老鈴木氏が火急に会いたいとのことであった。私は中座して、丸の内から車をとばせて大井の折口家に行くと、鈴木氏は、先師全集刊行会の経緯を話し、結論的には、「前にお話もあったことだから、この際中央公論社に刊行を引きうけて貰えば幸いです」ということであった。数十巻の全集はたいへんだが、結局会社も引きうけることとなり、話は正式に決定して、刊行会と社との共同責任の形で三ヵ年余にわたって厖大な全三十二巻を世に送ることとなった>(松下英麿『去年(こぞ)の人――回想の作家たち』、中央公論社)
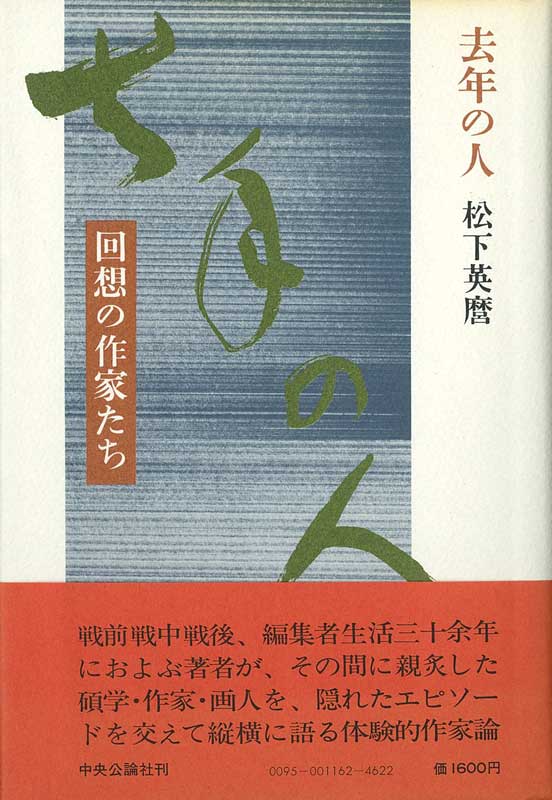
岡野さんは刊行会の編集室主任に就いたのです。この全32巻の全集は、私の大学時代に中公文庫に入りました。毎月1冊ずつ買い求めて、全巻揃えたところまでは良かったのですが、結局それを積み上げたまま、10数年後にそっくり人に進呈しました。ささやかな挫折体験として忘れられない一事です。
文庫版全集を手放した頃、私が住んでいたのは品川区西大井4丁目という所で、JR大森駅からゆるやかな坂を上り、ちょうど上りきったあたりでした。折口邸があった「品川区大井出石(いづるいし)町5052」は、現住所でいうと、西大井3丁目。“指呼(しこ)の間”といってもよさそうなすぐ近所に、折口、岡野の師弟が暮らしていたのです。
大森駅に向かって坂を下りながら、何度も思い浮かべた文章があります。小林秀雄の『本居宣長(もとおりのりなが)』(新潮文庫)の冒頭の一節です。少し長いのですが、そのまま引用いたします。
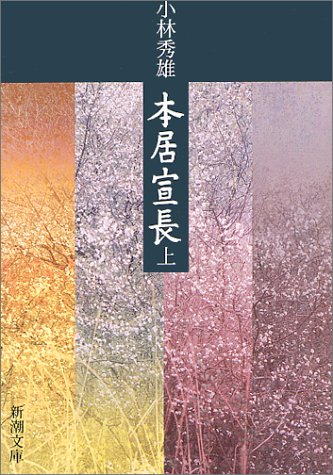
<本居宣長について、書いてみたいという考えは、久しい以前から抱いていた。戦争中の事だが、「古事記」をよく読んでみようとして、それなら、面倒だが、宣長の「古事記伝」でと思い、読んだ事がある。それから間もなく、折口信夫氏の大森のお宅を、初めてお訪ねする機会があった。話が、「古事記伝」に触れると、折口氏は、橘守部(たちばなもりべ)の「古事記伝」の評について、いろいろ話された。浅学な私には、のみこめぬ処(ところ)もあったが、それより、私は、話を聞き乍(なが)ら、一向に言葉に成ってくれぬ、自分の「古事記伝」の読後感を、もどかしく思った。そして、それが、殆(ほとん)ど無定形な動揺する感情である事に、はっきり気附いたのである。「宣長の仕事は、批評や非難を承知の上のものだったのではないでしょうか」という言葉が、ふと口に出て了(しま)った。折口氏は、黙って答えられなかった。私は恥かしかった。帰途、氏は駅まで私を送って来られた。道々、取止めもない雑談を交して来たのだが、お別れしようとした時、不意に「小林さん、本居さんはね、やはり源氏ですよ、では、さよなら」と言われた。>
ほぼ日の読者には、小林秀雄というと、「小林秀雄、あはれといふこと。」の筆者と勘違いする人がいるかもしれません。が、こちらは1983年3月1日に没した批評家の小林秀雄です。当日の朝日新聞夕刊1面に「近代批評文学の構築者」として大きく訃報が載ったその人の、畢生(ひっせい)の大業が『本居宣長』という作品です。
文中にある折口邸訪問は、1950年か、51年と目されます。岡野さんがまさに折口家にいた時期です。ところがなぜかこの出来事を、おそらくどこにも岡野さんは書いておられません。わずかに「國學院雑誌」(第111号、2010年1月15日発行)の座談会「小林秀雄の思想と生活――國學院大學における昭和40年11月の講演をめぐって」で発言されているくらい。他には、折口信夫『日本文学の発生 序説』(角川ソフィア文庫)の解説で、三浦雅士さんが「はっきりとした記憶」として“岡野情報”を伝えているくらいです。
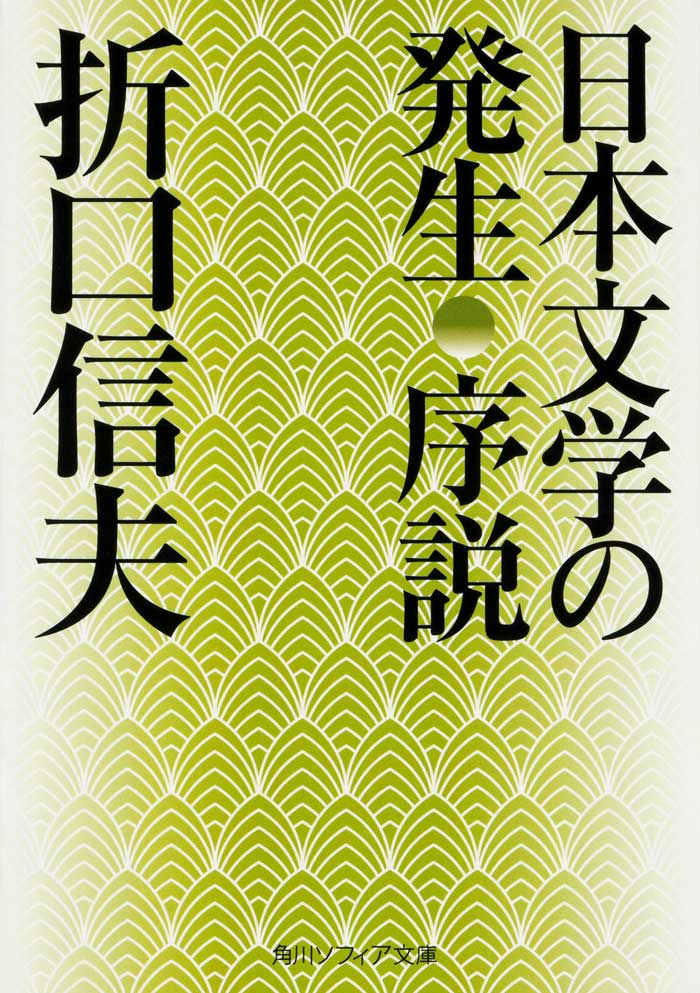
岡野さんは二人が対面している場にお茶を運んでいます。そればかりか、何を話しているのか気が気でなく、何度もお茶を換えに行ったと語ります。大森駅に送る際もお供をしています。そして、決定的な場面――。
<「小林さん、本居さんはね、やはり源氏ですよ、では、さよなら」という言葉は明瞭に記憶していて、それは折口が、改札を通り過ぎた小林をわざわざ呼び戻したうえで、はっきりとそう告げたからだという。>(三浦雅士、前掲書解説「凝視と放心」)
この重要なひと言が発せられた現場に、岡野さんは立ち会っていたのです。
宣長といえば、神官を養成する伊勢の神宮皇學館普通科(中学部)に学んでいた当時、岡野さんは毎年、宣長の命日が近づくと、大八車に山桜の苗木をのせて、秋の伊勢平野を行軍し、山室山に詣でるのが年中行事だったといいます。
山室山とは、伊勢松坂の人である宣長が、松坂城址に近い本居家の菩提寺とは別に、自ら望んで造らせた墓所があるところです。もちろん、小林秀雄は訪れています。
<苔(こけ)むした石段が尽き、妙楽寺は、無住(むじゅう)と言ったような姿で、山の中に鎮(しずま)りかえっていた。そこから、山径(やまみち)を、数町登る。山頂近く、杉や檜(ひのき)の木立を透かし、脚下に伊勢海が光り、遥かに三河尾張の山々がかすむ所に、方形の石垣をめぐらした塚があり、塚の上には山桜が植えられ、前には「本居宣長之奥墓」ときざまれた石碑が立っている。簡明、清潔で、美しい。>(小林秀雄『本居宣長』)
宣長は、自分の葬儀や墓に関する詳細な遺言状を用意しました。なきがらは松坂の町から8キロほど隔たった山室山のいただきに、山桜を周囲にめぐらせた墓域をもうけて収めるように、と指示しています。
しき島のやまとごころを人とはば朝日ににほふ山ざくら花
自画像の上に賛した宣長のこの歌に、「世評ほどの魅力を感じない」と岡野さんは述べますが、最晩年の宣長には、「老いのならいのわびしい夜ごと夜ごとに、心に浮かぶ桜の花のイメージばかりを歌に詠みつづけた『枕の山』という三百首ほどの作品」があるそうです(岡野弘彦「宣長と桜」、『歌を恋うる歌』中公文庫)。

中学生だった岡野さんは、この山室山に年に一度、山桜の苗木を運んでいたわけです。この時、生徒から募った歌の中で出来のいいものを、教師が宣長の墓前で読み上げたそうです。「わりあい私の歌が選ばれることが多くて」と岡野さんはユーモラスに語ります。
予習茶話会では、岡野さんの自伝的エッセイ『花幾年(はないくとせ)』を手がかりに話を進めようかと思っています。読み返しながら、改めて名品だと感じる随想集です。
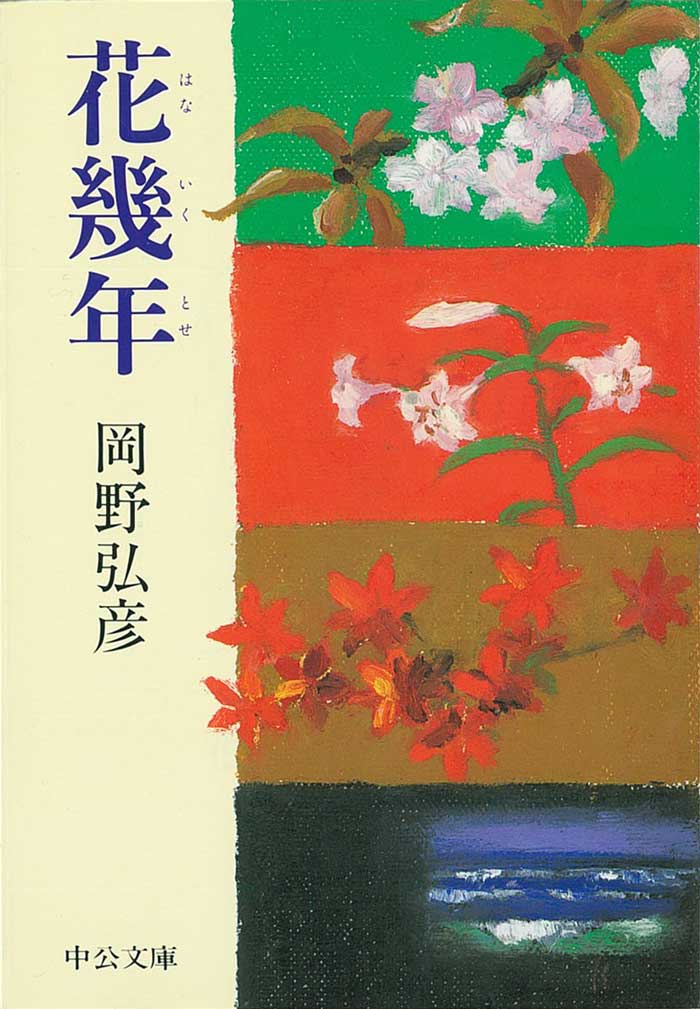
2019年1月10日
ほぼ日の学校長













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。