ほぼ日の学校長だよりNo.126
上野誠さんからのメール
前回、『万葉学者、墓をしまい母を送る』(講談社)という本を紹介したところ、著者の上野誠さんから、メールをいただきました。最後に、気になるひと言がありました。

<以上の文章は、ネットに公表していただいても結構でございます。なにか著者返信のようなかたちで、公にできるのなら、どうかお願いいたします。>
そして、トメの文章が以下でした。
<私のほぼ日の講義がステイホームの多少のお役に立っていることは、人生の名誉かもしれません。>
うーッ、泣けます! こういう決め台詞で締めるところが、上野さん、ニクイお方です。
「万葉集講座」の第1回で、シェイクスピア研究者の河合祥一郎さんを特別ゲストとして招き、「万葉集とシェイクスピア」という空前絶後、世界初のアクロバット講義を実現した上野さんです。私信を公表しても構わない、というお誘い(挑発?)を見過ごしては、いかにも「もったいない」と思うのです。

そこで、上野さんのメールを、まずはご披露いたします。
<このたびは、すばらしい書評をありがとうございました。
ネットでしかできない書評というもののすばらしさを知りました。
つまり、本というものが、ネットを媒介として、繋がるように編集できるのですね。
私は、テレビを見ても、映画を見ても、そこから得た知識をもとに、Amazonで本を買うのですが、ネット書評の場合は、そういうサーフィンができるわけですよね。
それにしても、的確に読んでいただき、ありがとうございます。
自分としても、なかなか捉えどころのない本なのです。
が、しかし。最近は、学者が小説を書くようですし、小説家が書いたものでも、データを駆使したものが多くなっています。
実証的学問=論文、想像力=詩や小説、という役割分担が少しずつ崩れているような気がします。
つまり、ミシェール・ウェルベックが示した近未来像と、社会学者の考える近未来像が無縁であるはずはないわけです。
私の場合、自分が背負ってきた学問というものの延長線上にあの本があるわけですが、論文にも小説にもならなかったというのが、偽らざるところです。
でも、書きたかったのです。
どうしても、多くの人に、知ってほしかったのです。
織田信長と豊臣秀吉と徳川家康を繋いだら歴史になるのか。
つまり、資料に残る歴史とは「公」の時間でしかありません。
その背後には、膨大な「私」の時間があります。
私は、『万葉集』の研究を通じて、膨大な「私」の時間にアプローチする方法を考え続けて20年になりました。
『万葉文化論』の「万葉びとの洗濯」などは、その好例です。
いつ、どこで、だれが、どのように洗濯し、その洗濯についてどのように思ったのか。
それだって、小さな歴史だと思います。
いや、それこそが、歴史そのものかもしれません。
私たちにとっては、国連決議や、国会の議決、閣議了承よりも、どうやったら楽に洗濯できるか、どんな洗濯洗剤を使えば色落ちしないか、の方が、重要かもしれません。
「公」の時間というものは、そういう私的な時間の海の中に浮かぶ木切れのようなものだと思います。
河野さんの書評を読みながら、自分のやりたかった仕事が朧気ながら見えて来たような気がします。>
ミシェール・ウェルベックをご存じない方にはそれぞれお調べいただくことにして、前回は書影のみの紹介となった『万葉文化論』(ミネルヴァ書房)について少し説明したいと思います。

実は、この900ページ近い大著が、「母親の残した全遺産を投入」して成った論文集であることを、『万葉学者、墓をしまい母を送る』の「あとがき」を読むまで知りませんでした。
「私は、自分の学問的思惟が、著作を通してしか後世に残らないことを知っている」
「一冊にまとめたのは、学問人生の残り時間を計算してのことである」
こう述べられた『万葉文化論』は、古代の人々の生活と心の諸相に迫りながら、『万葉集』の歌を読み解こうという試みです。
あるいは、『万葉集』の歌を手がかりに、日本人の文化や心性(マンタリテ)を古代にさかのぼって探求しようという野心的な研究です。
論文集としては型破りの、しかし感動的な「あとがき」は、上野さんの思いの丈を伝えてくれます。その一部を引用します。
<残念なことに、学問領域を越境してしまう万葉文化論の追随者はいないようである。しかし、私は、表現を支える文化的側面の研究こそ、現今の万葉研究の喫緊の課題である、と考えている。今、万葉文化論は絶対に必要な研究だと考えている。だから、流行とは無縁に、独自の道を歩んで、論文を書いてきてよかった、と思う。いや、そう思いたい。だから、たとえ、研究が破綻したとしても、この旗を降ろしたくはない。それが、私のプライドだ。>
これを読んだ上で、「万葉びとの洗濯」に話を移します。近年、アカデミズムの世界では、論文がどれだけ引用されるかが業績評価の対象になっています。この論文集のなかでも引用実績の多いものと少ないものがあるのだとか。引用実績が一件もない論文であっても、「生みの親たる私にとっては、いとし子だ」。そして、「万葉びとの洗濯」は、「引用実績が一件もないけれど、秘かに自愛している論文」なのだ、と。
「洗濯」といえば、『万葉集』巻1の28。いまの季節にふさわしい、持統天皇のあの歌があります。
春過ぎて 夏来(きた)るらし 白たへの 衣干したり 天(あめ)の香具山
青い空、輝く緑に映えて、「白」が目にも鮮やかです。
 藤原京跡から香具山を見る(「万葉集講座」奈良ツアー)
藤原京跡から香具山を見る(「万葉集講座」奈良ツアー)
さて、上野さんの論文ですが、「あとがき」の文章に、著者のこの論文に寄せる愛着、「時空を越えてどこかにいるはず」の共鳴してくれる読者への期待が述べられています。
<衣服に関わる労働は、前近代の社会においては女性に独占されていた。女たちは、ひたすら、糸を紡ぎ、機を織り、服に仕立てた。麻をはじめとする繊維は、曝(さら)せば曝すほどに白くなる。女たちが、川に浸り、布を干すという労働を果てしなく繰り返して、ようやく白い布地が生まれるわけである。したがって、布地の白さは、女たちの重労働の証なのであった。だから、より白い布を恋人に贈りたいと歌えば、女の愛情表現になるのだ。また、男が曝された布の白さを歌えば、それもまた、女を思いやる愛情表現となるのである。旅先の男が服に付いた垢を歌い、その洗濯を思いやることは、家なる妹(いも)を思う表現となるのも、同様だ。従来の色彩表現論には、こういった労働文化の観点がなかった。引用の実績はまだないけれど、歌と生活を往復することによって、表現の本願とするところを突き止めた論文だと、私は秘かに思っている。引用実績がまだないがゆえに、この論文のことを、私はせつないほどに愛おしく思う。>
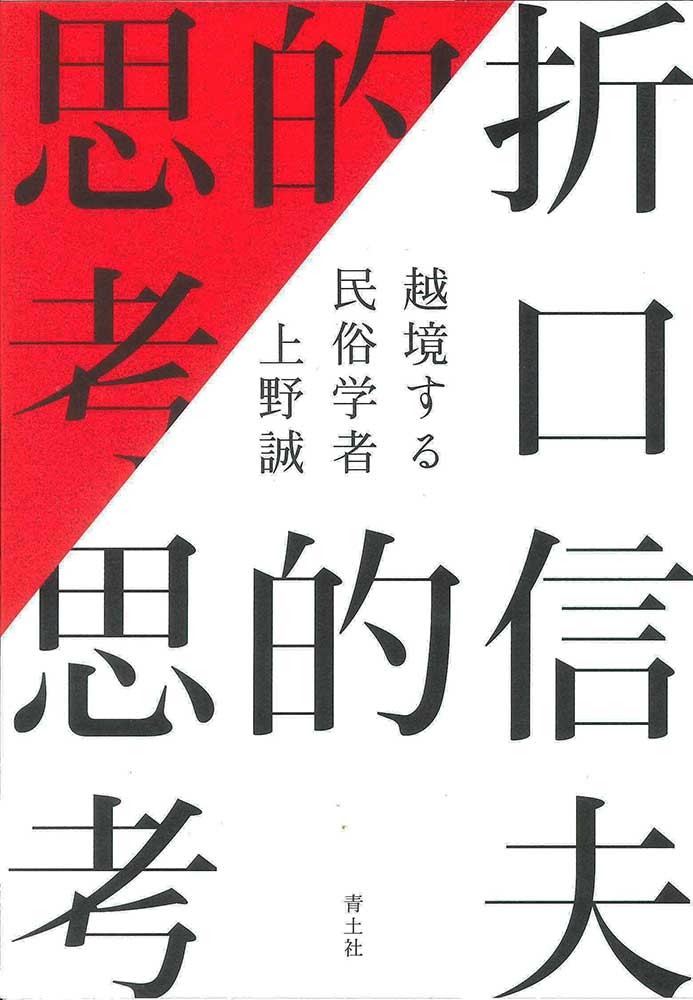

「万葉びとの洗濯」に引用されているのは、新羅(しらぎ)の国に派遣された「遣新羅使」一行の歌です(*)。736年(天平8年)6月に新羅に向けて旅立った、総勢おそらく200名ほどの使節団は、なんとも不運で苦難に満ちた旅を強いられます。秋には、任を終えて帰国できるだろうと思っていたところ、そもそも出航が遅れた上に、瀬戸内海を西へ航海する途中、いまの山口県徳山のあたりで逆風に遭い、大分県の中津付近まで流されます。
ようやく落ち着いた先で、ひたすら恋しく思うのは都(平城京)のことであり、そこに残してきた妹(恋人である女性や妻)のことです。3首が紹介されています。
A 妹を思ひ 眠(い)の寝らえぬに 暁の 朝霧隠(ごも)り 雁がねそ鳴く
B 夕されば 秋風寒し 我妹子(わぎもこ)が 解き洗ひ衣 行きてはや着む
C 我が旅は 久しくあらし この我(あ)が着(け)る 妹が衣の 垢付く見れば
(巻15、3665~3667)
Aは、「あの人のことが恋しくて、よく眠れない夜を過ごしていると、明け方の朝霧に包まれて雁の鳴く声が聞こえてきた」という歌です。『万葉集』の雁は秋の来雁を意味するので、秋の深まりを知ったというわけです。秋には都に戻れると信じていたのに、まだ筑紫で足踏みしている、というところで、「旅路のはるかなることと、妹との別離の時間」が意識にのぼります。
そして、この歌を受けて「夕されば 秋風寒し」と歌い起こすBの歌につながります。「解き洗ひ衣」とは、いわゆる「洗い張り」のことであり、着古した衣の縫糸をいったんほどき、「解き洗ひ」できれいに洗濯してから、さっぱりと仕立て直した着物です。
Aを受けて、夕暮れになると秋風が寒い、とまず歌い、早く家に帰って、愛しい妻が解いて洗って仕立て直してくれたきれいな着物を着たいものだ、と願います。
そして、別離の時間の長さを思い、望郷の念を、衣を通して歌ったところでCの歌につながります。万葉びとは、「しばしの別離に対して、互いの下着を贈答しあった」そうですが、いま自分が身につけている妹から贈られた衣の汚れに、長旅の辛さ、別離の久しさを嘆いています。
「洗濯」をはじめ衣服にかかわる家事労働は、古代の社会においては、女性の重要な労働でした。万葉歌では、「洗濯」が旅先の男たちと、家を守る女たちの心をつなぐものとして歌われます。そして、「洗濯」によってきれいに洗い落とされる「垢」に対置された「白」――「白たへ」の「白」――が、「無垢」をシンボライズした色として光り輝いている、というのが上野さんの読み解きです。
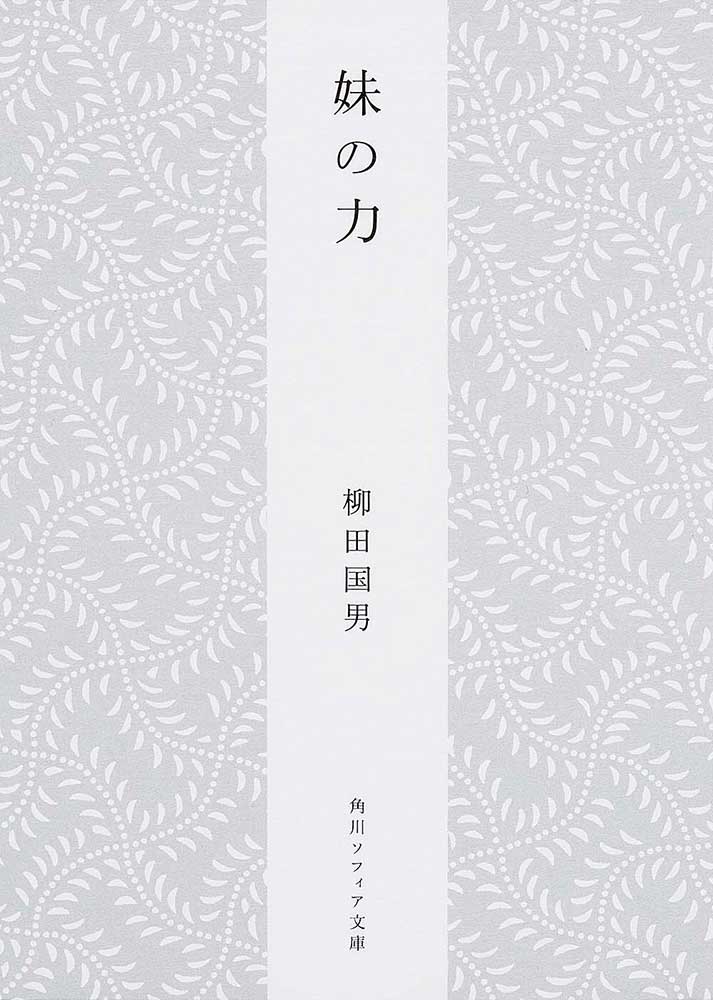
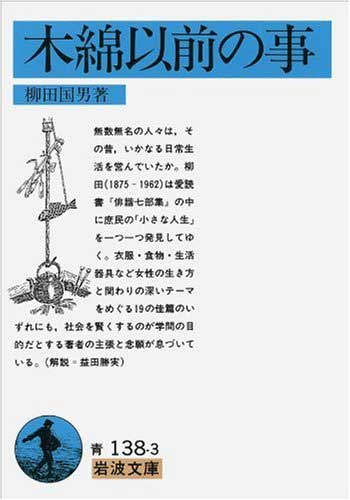
古代の人々の暮らしと心性、表現性の3つの次元で、『万葉集』の歌を実感しようというのが『万葉文化論』の試みです。上野さん言うところの「小さな歴史」であり、さらに言えば「いまの私」が実感できる、万葉びとたちの心のありようを描いた歴史です。
さて、ここまで書いてきて、前回書き切れなかった部分をひとつ紹介して、締め括りにしたいと思います。88歳まで一度も郷里である福岡を離れたことがなかった母親を、上野さんが奈良に連れてくる場面です。
「お母さん。しばらく、奈良に来(こ)んね。よか病院のあるとよ」と誘い、お母さんは奈良に転居するわけですが、引っ越し当日、予期せぬトラブルが生じます。お母さんが、「福岡を離れることにはそもそも同意していない」と言い出すのです。
準備万端整って、当日は「意気揚々と母のいる短期ステイの介護施設に乗りこんだ」はずが、そこからすったもんだが始まります。いっこうにラチがあきません。そこで上野さんは、息子にしか許されない“奥の手”を使います。
「では、くさ。奈良行きはやめようたい。でも、この施設は、今日で終わりやけん、別の病院に替わらないかん。ちょっと遠くのね」
こうして介護タクシーで駅まで行き、新幹線のグリーン車に飛び乗ります。
<十二時過ぎ、ゆっくりと「のぞみ」は動きだした。新幹線が小倉に着くと、母は降りようとする。小倉の病院だと思ったのであろう。私は、慌てて、「もう少し遠かとこばい」と言う。ならば、広島か、ならば岡山かぁ。息子はまだまだと言う。母は、それならどこと、不安な顔をする。(略)
もう、新大阪も過ぎた。京都で下車し、近鉄特急に乗せたとき、母はすべてを悟ったようだ。そして、一言、こう言った。
「誠、そんなら、何ヵ月、おればいいとね。奈良に」>
上野さんは、「福岡の病院に空きができたら、すぐたい。すぐ帰るとよ」と答えます。もちろん母親が福岡に帰ることはないでしょう。そんなことは、あり得るはずがないのです。
その問答は、死の数日前まで続きます。
母 いつ、福岡の病院は空くとね。
息子 まだ、空かんとよ、それが。
<あるときは、とげとげしく言いあったし、あるときは、挨拶のように、この問答をかわしあった。数百回か、数千回か。しかし、これしか、道がなかった、と私はいまでも信じている。>
母上は、7年間を奈良で過ごし、2016年(平成28年)に逝去されます。
<七年前、私は母を騙して奈良に連れてきた。その日から、とにかく、ものごとを割りきって考えるようにしてきた。とにかく、できることはたくさんしてやって、楽しませて、楽しませて、歓楽を尽くさせて死なせたい、と。
しかし、自分の家庭が壊されたり、自分の仕事のペースが乱れることは、絶対にしたくなかった。母も、そう思っていた、と信じたい。そのためには、どうすればよいのか。私は必死に考えた。それは私のこれまでの人生のなかで、最大のプロジェクトであり、私は大作戦と呼んで、人生の苦境を秘かに楽しんでいるところもあったのだ。>
「己の心を通じて、心性の歴史を描きたい」「個人的体験を軸としながらも、その共同体や集団の歴史を踏まえた、小さな小さな歴史」を書きたい――こうして生まれたのが、『万葉学者、墓をしまい母を送る』(の記でした。
 飛鳥を一望する甘樫の丘にて(「万葉集講座」奈良ツアー)
飛鳥を一望する甘樫の丘にて(「万葉集講座」奈良ツアー)
著者は今年7月に還暦を迎えます。兄上が59歳で逝き、恩師が61歳で亡くなり、「六十を前にして、どこか落ち着かない気分がわが胸を覆っている」と。
「私」が描く「死と墓をめぐる心性の歴史」も、この節目の意識が筆を執らせたと言えるでしょう。そしてもちろん、万葉学徒としての収穫の秋が、まさに訪れていることの自覚もまた――。
2020年5月21日
ほぼ日の学校長
*「万葉集講座」第1回で取り上げられた「君が行く 海辺の宿に 霧立たば 我(あ)が立ち嘆く 息と知りませ」(巻15、3580)の歌も、この「遣新羅使」の作品に含まれています。













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。