ほぼ日の学校長だよりNo.120
捨てる看護
窓から差し込む朝の陽光を浴びながら、自宅で迎えた安らかな永眠。
看取ったのは妻と、高校生、小学生の娘たちです。3人は拍手で送り出しました。故人が希望していた旅立ちの祝福――。
「これは、私の友人、森山文則さんの物語」とエピグラフに記された『エンド・オブ・ライフ』(佐々涼子、集英社インターナショナル)は、在宅での終末医療をテーマにした著者渾身のノンフィクションです。

主人公である森山文則さんは、それまで200人以上の終末期の患者を支えてきた、いわば看取りのエキスパートです。その彼が2018年8月、突然48歳の若さでステージⅣのすい臓がんを宣告されます。それから死に至るまでの8ヵ月あまり、揺れ動く彼の心の変化に目を凝らし、当人がどのように死を受け入れ、どのように人生の最期を迎えるのか、つぶさに描き出したのが本書です。
それとともに、主人公の心に深く刻まれたさまざまな人たちの「命の閉じ方」を物語の横糸として編みながら、過去と現在が行き交うように語られます。
著者が在宅医療の取材を始めたのは、7年前のことです。
<二〇一三年当時、私は駆け出しのノンフィクションライターだった。『エンジェルフライト国際霊柩送還士』という、海外で客死した人々の遺体を運ぶ仕事を描いた本でノンフィクション賞を受賞し、ようやく仕事が軌道に乗り始めた頃だ。次回作は、在宅医療について取材をしてみないかと、編集者に声をかけられたのが、森山との出会いのきっかけだった。
在宅医療とは、病気やけがで通院が困難な人や、退院後も継続して治療が必要な人、自宅での終末医療を望む人などのために、彼らの自宅を医師や看護師が訪問して行う医療だ。>

取材先に選んだのが、森山の勤務していた京都の渡辺西賀茂診療所です。ユニークな取り組みを行なっていました。在宅患者の「最後の希望」をかなえるために“ボランティア”を買って出るのです。
37歳の末期がんの女性患者がいました。京大病院に入院していましたが、幼い娘と約束をした潮干狩りに行きたいと言って、一時帰宅します。訪問看護の標準メニューに、個人的な家族旅行への同行は、もちろん含まれません。
ところが、この診療所は京都から愛知県知多半島の南端まで、片道約180キロの“危険”な旅に、往診車を一台同行させます。3人のスタッフが9本の酸素ボンベや医療器具を積み込み、万一の事態に備えます。そして、家族の“思い出づくり”を無事に実現するのです。
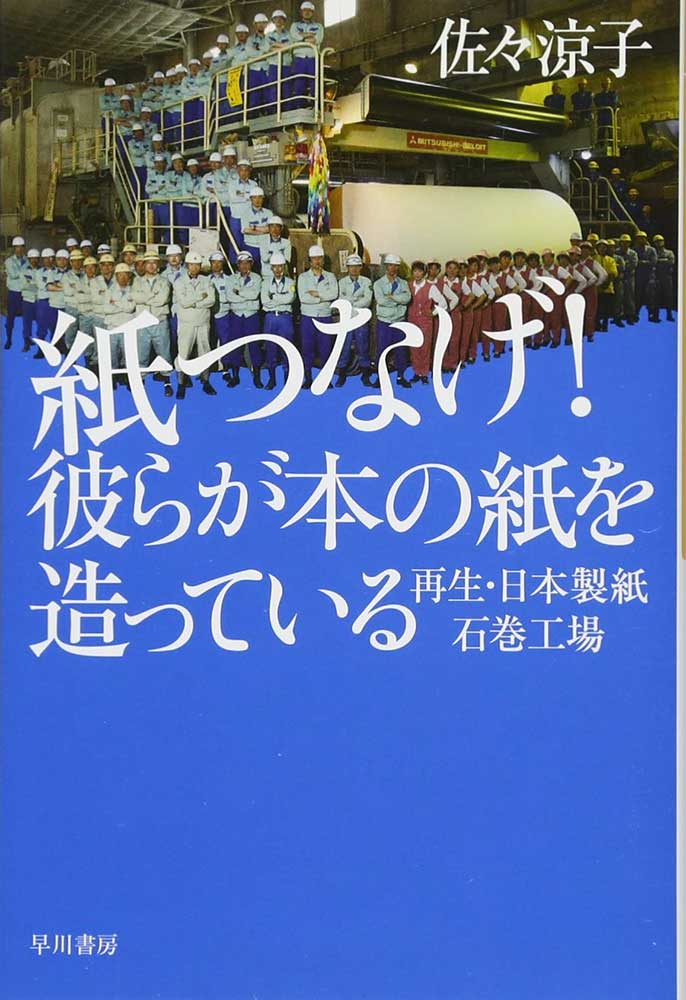
同日21時40分、自宅に戻り、長い一日が終わります。その夜、駆けつけた医師たち、家族の見守る中で、その女性は旅立ちます。母親としての強い愛情と、自らの意志を貫く「行動する勇気」を周囲の人たちの心に刻んで――。
「僕らは、患者さんが主人公の劇の観客ではなく、一緒に舞台に上がりたいんですわ。みんなでにぎやかで楽しいお芝居をするんです」
診療所の院長は、このように自分たちの役割を語ります。取材を始めて間もない著者も、この潮干狩りに参加しました。スタッフのひとりが森山でした。髪は五分刈り、細身で物腰が柔らかく、著者の目には“禅僧”のように映ります。
森山が“ボランティア”について語ります。
「この診療所はこういう時、交通費も人件費も患者さんからは取りません。不思議な行為でしょう? どうしてそこまでやるのだろうと思われますよね。それは一見なんの利益もない行為だと思うかもしれません。でも、この渡辺西賀茂診療所は、それ以上の見えない何かを、患者さんからいっぱいもらってきたんです。(略)
おせっかいすることには大変なことがたくさんあります。なにか行動しようと思えば、軋轢(あつれき)もある。でも、得られるものはそれ以上です。それを知っているから動いてしまうのかもしれません」
わがままで手を焼かせる患者もいます。不条理な運命と最後まで折り合いがつけられず、自死した男性もいました。美しい話ばかりではありません。きれいごとでは語れません。さまざまな在宅医療の現場に立ち会いながら、次第に著者の目は開かれていきます。
<そもそも在宅医療に興味を持ったのは、当時私の母が在宅で療養していたからだ。
要介護五。母が自分で動かせるのは瞼だけだ。私は母の命の選択に立ち合ったことがある。医師に「胃ろうをつけますか?」と決断を迫られたのだ。母は運動機能に障害があり、顎をうまく動かせない。すでに食事を咀嚼(そしゃく)するのが難しくなっていた。
父の決断は早かった。迷うことなく胃に穴を開ける胃ろうを選択した。それ以来、三六五日、二四時間、父が介護を担っている。>
この時(2013年)、すでに7年間の介護生活が続いていました。淡々と、しかしこれ以上なく献身的に、寝たきりの妻をケアする父は、すっかり介護のスペシャリストでした。そのことに敬意と感謝を覚える一方で、はたして誰もがそこまでできるものなのか? 自分のように仕事を持つ者が、家族を家で看られるものか? と、著者は問いかけずにいられません。

他の家ではどうしているのか? その実態が知りたくて、飛び込んだ先が渡辺西賀茂診療所です。
しかし、取材を重ねるほどに見えてくるのは、「病状や、家庭環境、協力者の有無によって状況は変わる」という当たり前の事情です。
したがって、在宅医療の専門家がいくらその「素晴らしさ」を讃えても、現実の厳しさのほうに目が向いて、どう書き進めていいのか分からないまま、原稿は宙ぶらりんになっていました。
そんな時に、森山にがんが見つかります。すい臓がんを原発とする肺がんで、5年生存率が1.5%の末期がんです。連絡を受けて駆けつけると、森山は意外な言葉を口にします。
「僕はあきらめていませんよ」
「僕は生きることを考えています」
彼のこれまでの仕事は、「患者が死を受容できるように心を砕き、残された時間を後悔のないように生きるよう導くこと」でした。

つまり、「死を受け入れ、準備期間を大切にしてもらうこと」を仕事にしてきた森山が、「死を受け入れることを、きっぱりと拒んで見せた」のです。そして、自分の最後の仕事として「将来、看護師になる学生たちに、患者の視点からも在宅医療を語りたい。そういう教科書を作りたい」と、著者に共同執筆を持ちかけます。
「予後を気にして生きていたら、それだけの人生になってしまう。僕は僕自身であって、『がん患者』という名前の人間ではない。病気は僕の一部分でしかないのに、がんの治療にばかり目を向けていたら、がんのことばかりを気にする人生を送ることになってしまう。闘うのではない。根治を願うのでもない。無視するのでもない。がんに感謝しながら、普段はがんを忘れ、日常生活という、僕の『人生』を生きていきたいんです」
「‥‥僕は在宅看護をやっていて本当によかった。患者さんたちが、僕に教えてくれたことがたくさんあります。彼らは見せてくれたんですよ。途中つらいところを通ったとしても、最後はみな、穏やかに笑いながら逝くんです」
「僕は、子どもたちに何が残せるのかな‥‥。人は、生きてきたようにしか死ぬことができない。でも、ひょっとしたら病気がターニングポイントになるかもしれませんよね。このターニングポイントの中で、自分も周りも変化して、今まで生きてきた感覚とまったく違う輝きがそこに生まれるかもしれないと思うんです」
こうして森山と最期の8ヵ月を過ごしながら、看取る側から看取られる側に立場を変えた彼が、やがて来る死を予感して、「スピリチュアル・ペイン」――死期を悟った人が「自分の人生の意味はいったい何だったのか?」と魂の根源的な痛みと向き合う――のなかで、揺れ動き、苦しみ、なんとか言葉を残そうとする懸命な姿を見守ります。
著者は内心、森山のこれまでの看取りの経験が「彼自身をも救うのではないか」と期待していました。ところが、病状が進むにつれ本人は仕事から遠ざかり、抗がん剤治療を途中でやめ、医療的処置よりも自然治癒力に賭けたいなどと言い出します。
共同執筆を持ちかけた「実践看護」の本についても、一向に筆を取ろうとはせず、著者のインタビューに答える気配も見せません。それでいて、著者との仕事に希望を抱いていることは明らかです。
生きる意欲と迫りくる死の不安のなかで揺れ動く森山の姿を受けとめながら、いつ本音を語り始めるのかと、じっと言葉を待つ著者の姿にも打たれます。
やがて傍目にも、残り時間の少ないことが明らかになります。
<私はこれが最後のチャンスだと思いながら声をかける。
「在宅医療について語ると言われて今までついてきました。でも、まとまった話は今まで聞いてないですよね。どうですか。話したいことがありますか?」
森山は肩で息をしながら、ふふふっと笑った。
「何言ってんですか、佐々さん。さんざん見せてきたでしょう」
「え?」と、声にならない息で私は聞き返す。
「これこそ在宅のもっとも幸福な過ごし方じゃないですか。自分の好きなように過ごし、自分の好きな人と、身体の調子を見ながら、『よし、行くぞ』と言って、好きなものを食べて、好きな場所に出かける。病院では絶対にできない生活でした」
「‥‥、そっか」>
著者ははたと気づきます。抗がん剤をやめた後の森山は、「まるで夏休みの子どものように」その日、その日をひたすら楽しみ、医療も看護も関係なく、ごくありふれた日常を、ごく普通に過ごしていました。
それが、200人以上を看取ってきた森山が選んだ最期の日々の過ごし方です。「予後何日という予測を捨て、ステージⅣであることを忘れ、その日、その日をひたすら楽しみ、がんの言い分を聞き、ただただ、真剣に、懸命に、自然治癒を信じて遊び暮らした」――そのプロセスをずっと間近で見せてくれていたのだ、と。

<「今を生きよ」と彼は私に教えてくれた。「捨てる看護」と彼は言ったが、その言葉をそっくり実践したのだ。>
「病人だからベッドに寝て、病院食を食べるのではなく、医療や看護といったフレームワークをとっぱらったところ」に、自分の人生を見出したのだ、と彼は言います。これこそ「在宅」ゆえの自由であり、幸福なのではないか、と。
<終末期の取材。それはただ、遊び暮らす人とともに遊んだ日々だった。そして、人はいつか死ぬ、必ず死ぬのだということを、彼とともに学んだ時期でもあった。たぶん、それでいいのだ。好きに生きていい。そういう見本でいてくれた。>
どう命を閉じれば良いのか。その答えは一様であるはずがありません。ただ、多くの人は標準治療の“ベルトコンベアー”に載せられて、生きる期間も、命の閉じ方も、「自由にのびのびと」というわけには行きません。
患者が「人生を生ききった」と満足できる、そんな「エンド・オブ・ライフ」こそが価値なのではないか。

森山が「捨てる看護」と言ったのは、これまでの医療や看護のカテゴリーにはおさまらない、そんな新たなサポートを「もし自分が治ったら」試みたい――そういう果たせぬ夢だったともいえるでしょう。
<亡くなりゆく人は、遺される人の人生に影響を与える。彼らは、我々の人生が有限であることを教え、どう生きるべきなのかを考えさせてくれる。死は、遺された者へ幸福に生きるためのヒントを与える。亡くなりゆく人が、この世に置いていくのは悲嘆だけではない。幸福もまた置いていくのだ。>

著者の佐々涼子さん
森山文則は生き続けています。本書を書いた著者の中に、そして彼と縁を結んだ家族や、多くの人びとの心の中に――。
2020年4月9日
ほぼ日の学校長













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。